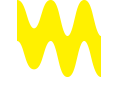2017.10.04
3DCGの少女とのコミュニケーションから考える、エモーショナルリアリティの作り方
〜ゲスト:石川晃之、石川友香、仲谷正史/ホスト:南澤 孝太〜
“わざ”にフォーカスし、Haptic(触覚)の研究やデザインに携わる方々をゲストに開催するシリーズイベント「Haptic Design Meetup」。2017/10/4に実施したVol.4は「Haptic ×(Emotion)Design」をテーマに行いました。
イベントのオーガナイザーである南澤孝太氏をホストに、仲谷正史先生(慶應義塾大学 環境情報学部 准教授/JSTさきがけ 研究員)と石川晃之氏・石川友氏(telyuka )を交えて行われたクロストークの模様をお届けします。
慎重で綿密な観察によって突き詰められた3DCGによる少女Sayaの造形が、触覚を含めた身体感覚にどのように影響するするのか、また彼らのような存在が実在性を高めることで人間の行動が変容するのかなど、人間の内面や行動原理に関わる興味深いトークが展開されました。
※ぜひDESIGNER’S FILEの「石川晃之さん/石川友香さん」、「仲谷正史先生」の回をご覧の上お読みください。
※肩書は2017年10月4日登壇当時のものです。
観察の追求による実在性の表現
人間は人間の質感を一番好むのではないか

ー左から南澤先生、仲谷正史先生、石川友香さん、石川晃之さん
(南澤)telyuka さんからはSayaの17歳という、はかなさとか不確実性という言葉を使ってらっしゃいましたけど、そこを表現するときに、ものすごいディテールを観察していること、それをさらにアナトミー、人間の身体の中の構想まで含めて作ることで、その実在感を作っているところが興味深かったです。その「胸キュン」ってのは身体感覚そのものだと思うんですけど、そこの情動っていうのが、まさに仲谷さんのおっしゃる「体は気づいている」という、キュンっていう触感そのもの、身体感覚っていうところをどう作るかというお話なのが非常に面白いなと感じながら伺ってました。
伺いたいことがいろいろあるんですが、観察の話からいきましょうか。スマホ用のマクロレンズがありますよね。仲谷さんはあれを持ち歩いてた時期がありましたが、今も持ち歩いてるんですか。
(仲谷)持ち歩いています。
(南澤)じゃあ、今もですね。いろんなものを超マクロで撮ってるんですよ。このテクスチャーの、この感じがいいねって言いながら、すごいマクロで撮ってたっていうのを覚えてるんですけど、あの感覚から見て、Sayaのあのものすごいディテール感ってどういうふうに感じられました?
(仲谷)肌のあの透き通る感じと、静脈の感じがやっぱり僕はぞくっとするなと。というのは、僕も化粧品の会社に勤務していた時期があるので、他の人の顔を接近した距離で拝見する機会が多くありました。遠くから見ると平坦に見える肌も、細かな凹凸があったりとか、血管の色が見えたりっていうのが経験としてありました。、その中でも、肌の透明感として、静脈が肌をとおして見えている感じが、人間の生き物らしさというか、本当に存在をしている「リアリティ感」を醸し出してるんじゃないかなというふうに、僕は感じました。
(南澤)静脈ときましたか。telyuka さんいかがですか。
(telyuka 石川 友香(以下友香))人間は人間の質感を第一に好むんじゃないかと思っています。それは愛とかそういったものも関連すると思いますが。女性の肌質感に関しては男性女性共に強く美を求めるものだと感じています。例えば昔から絵画等の巨匠の方々も追い求めているように思いますし、ほぼ裸の絵画も沢山あります、フェチや美しさの追求等が共存していて。昔からのアーティストの求めるテーマなのかもしれませんね。
触れ合うという行為が、
いかに相手の存在感を確信させられるか
(南澤)昔からのテーマっていうことでいうと、会社名Garateaというところの由来をさっき伺って、ちょっと面白かったのでもう一度説明していただいてもよろしいですか。
(友香)ガラテアはギリシャ神話で登場する名前ですが、ピュグマリオンという彫刻師がいます。その彫刻師がすごく腕がよく、あるとき女性像を作りますがその女性像に恋をしてしまった。そして、女神アフロディーテに命を与えてほしいと嘆願します。アフロディーテは、女性像に命を吹きこみ魂が宿ります。その娘の名前がガラテアと名付けられ、そのガラテアとピュグマリオンは結婚し幸せに暮らします。私たちが作る像もガラテアの様に命を吹き込み魂が宿れば・・と思い名前をつけました。
(南澤)まさに現代のガラテア、現代の彫刻ってことですよね。CGでディテールを吹き込める、突き詰める行為も、絵画の全盛期に絵を描くことで生命感を突き詰めるという行為も、恐らくその昔の彫刻も共通点が多く存在すると思います。基本的には同じ目標に対してただツールが変わっているだけなんだろうなと。
やっぱり求めているのは人間の生命感だったりとか、感情をいき交わせるような対象としての人間、ヒューマニティをどういうふうに作り上げるかっていうプロセスなのかなっていうふうに思うんですが、そこに触れる行為とか、触れ合うという行為が、いかに、どのぐらい相手の存在感というものを確信させられるかとか、そことの感情のつながりを生み出すかというのが、まさにその情動コミュニケーションのお話なのかなと思うんですけど。触覚、いわゆるテクスチャーというよりは、触れ合いそのもの、ぬくもりとか抱きしめられるとか、そういったところと、人と人との精神的なつながりって、何か関係性はあるのでしょうか?
(仲谷)僕の個人的な体験の話になりますが、以前、ハンドマッサージのボランティアに携わったことことがあります。それは岩手県の大槌町という震災後の津波で甚大な被害を受けた地域に設けられたコミュニティ・サポートセンターで開催されたイベントで提供した内容の1つでした。5分ほどの時間をかけて、大槌町近隣の地域に住む高齢者の方にハンドマッサージをして差し上げてました。そうすると、短い時間でも手があたたかくなってくるんですよね。また、お互いに手持ち無沙汰であるので、たわいもないお話をしたりします。、震災後に復興してゆくその時の大槌町がどのような様子なのかをうかがうこともありますが、もっと生活に身近な話、大槌町の山の幸の話をしたり、自然の豊かさの話をもうかがいました。そうすると、大槌町に長期滞在して活動しているメンバーでも聞いたことないようなお話をうかがえることもありました。触れるコミュニケーションによって、手だけなくて心も温まって、緊張感がほどけるということがあるのではないかな、と経験的に体感したことがあります。
ハンドマッサージを行うことで、精神的・生理的ストレス指標が下がるといった研究知見もあって、その効果については多くの人が認めることでしょう。ですが、そのような科学的エビデンスで測れないような、人の心や情動に働きかけて前向きに導いたり、社交を促す効果が、触れるということにはあるのではないかなと、僕は感じます。
(南澤)やっぱり近さを感じるんですね。触覚って人間の皮膚の上にある感覚なので、それは要はある意味、外から自分を守る感覚なんですけども、だからある意味、危害を加えるものを守るための感覚でもあるんです。なんだけど、そこが触れ合い続けることで、初めは何か温度差があったものが、同じ温度になって感じなくなるとか、相手からマッサージされて自分が感じているってことが続いてくことによって、その感覚ってのがどんどん、スムーズに、自分の身体に溶け込んでくると、相手の存在と自分の存在の境界が、ちょっと曖昧になってそこから何かコミュニケーションの扉が開くっていうようなことが起こるのかなと。
それをぜひSayaとのコミュニケーション、CGのキャラクターとのコミュニケーションでも、そういう自分との距離感がゼロになる感覚というのが作れると、もしかするとやっぱりその触覚っていうか、皮膚感覚を通じて、そこに存在、いわゆる物理的な意味では存在しない人であっても、触れ合える可能性があるかなと思うんですが、どうしたらいいんでしょうか。
(仲谷)技術的な話ですか?もう少し概念的な話ですか?
(南澤)どっちでもいいと思います。技術的な話をすると、多分、意外と簡単なようで難しい部分があるかなと思っていて、そこに技術の存在が見えてしまった瞬間に、実はだめなのかもしれない。そこに技術の存在を見せずに、直接的に触れ合って間に何もない、介在せずにそこと触れ合いが生じているって状況を作るのが肝な気がします。そもそも、どういう触感とかを伝えるのか、触感いうか皮膚感覚を伝えると、そういう情動的なコミュニケーション、生みやすいんだろうかと。
(仲谷)僕はSayaさんを見て思ったことは、彼女に触れるとどれぐらい冷たいのかな、あたたかいのかな、ということでした。触れることが良い方法であるのかはわからないですけど、少なくとも相手に触れると温度が相手に伝達しますよね。その温度が通じたっていう感覚が、何かその人と通じ合ったっていう実感につながるかしれません。体温を持っているということは、相手が生きているという認識につながるのではないかな、と、にわか話として僕は思いました。彼女は冷たいのでしょうか?
(友香)どうですかね。でも液晶さわったら温かいので。
(一同)(笑)
国による触れ合い方の違いを
いかに解釈し、Sayaのふるまい方に反映させるか
(友香)なのでちょっと仮想的に楽しんでもらえたら、と思うんですけど。そこの部分って、すごく私も考えてて、例えば触れ合うことって、アメリカの人とかって、最初にハグしたり、キスしたりっていうのを、すごくカジュアルにやられますよね。でも、日本はそこがカジュアルじゃない。じゃあ、Sayaと触れ合えるとなったときに、日本の人たちはSayaに触ってくれるかどうかっていうところを疑問に感じてまして、外国の方でしたら、もしかしたらハグしたりとか、そこまで突破できるコミュニケーションの術もあると思うんですけれども、そういう感覚ってどうなのかなって感じてます。
(南澤 )みんな、日本だと、すごいそーっと触りそうですよね。触っていいのかな、いけないのかなって、ほっぺにちょっと手を当てるとか、握手だったらやりやすいなって思うとか、ハグは確かになかなかしてくれないんですね。そこの辺りは確かに、もしかしたら触覚によるこういう情動コミュニケーションの文化差ってものすごいあるのかもしれない。それによって、僕らがもしかしたら、コミュニケーションそのものでも、そもそもの日本人とかそれこそ外国の方とでコミュニケーションの感覚は違うと思うんですけど、実はそこの皮膚感覚をどういうふうに使ってるかっていう、普段のそういう戦略で変わってきてるっていうのがあるかもしれないですね。
(仲谷)加えて、彼女のそばに立ったときに、人がどのような立ち姿をするのかについては興味深いと思います。特に日本人にとって、彼女の正面に立って直面するとして、どのような角度から彼女に近づいてゆくのかは重要になるかもしれません。相手の正面に立つということは、それなりの覚悟が必要だし、心理障壁の高いことだと思います。Sayaさんの臨場感を、正面に立つ人の立ち姿によって、測ることができるかもしれないと僕は感じました。。
(友香)ちょっとその話に近いかなと思うんでが以前、実は8Kモニターを縦型に使って、Sayaを等身大で描画したことがあるんですね。8KモニターでSayaを描画するとみんなどうなるのかなと思って、ある会社で見させてもらったんですが、みんなここぞとばかりに、写真をもう撮りまくるとか、液晶、つまり彼女の前に来て、ずっと見ているとか、普段17歳というその年齢の女の子を目の前にして、できないことをやるんですよね。
(一同)(笑)

CEATEC 2016 SHARP ブースにて披露された8KのSaya
(友香)それは、Sayaに心が入ってないとか、人間じゃないっていうところがあったりして。普段抑えているその欲望をここで発揮する、ということじゃないですけれども、もし、これに触覚がついていたら、みんなどうするのかなっていうのが、すごく興味がありますね。
(南澤)それができないところまでいきたいんですよね。
(友香)そうですね。
「触れてはいけない」という感情を
どのようにデザインするか
(南澤)それをしちゃいけない、って思えるような存在感を出すというのは結構、皮膚感覚のミッションなのかなっていう気がしていて。触れ合える存在じゃないと、確かにガラスの向こうの世界、自分たちの世界にはいないから、ある意味、何してもいいって思っちゃうかもしれないんだけども、それが触れ合えると、触れ合った瞬間に相手を傷つけることもできちゃうし、相手を押せば倒れるかもしれないって、そういう何かそこに傷つけられない存在として感じるっていうことでもなく、それを感じることによって、むしろそういう失礼なことをやらないとか、できないぐらいのとこまで持っていけると、面白いのかなっていう気がします。
仲谷さんの「体は気づいている」という言葉であったんですが、一つそれで思ったのが、人とコミュニケーションすることって、ドキドキすれば、自分自身も心拍が上がったり瞳孔が開いたりすると思うんですけど、多分見ている相手もそれを感じ取りながらコミュニケーションしますよね。ということは逆にそれはSayaちゃん側が、相手のことをちょっと見るというか、感じ取ることができると、もしかしたらそういったコミュニケーションやアプローチが変わってくるのかなと思いました。例えば、それこそ心拍だったり、相手のもうちょっと情動的な部分を取りながら、Sayaの行動を変えていくとかっていうのは、どうなんでしょう?
(telyuka 石川 晃之(以下晃之))そこはやはり技術的というか、ある意味動作、人間の所作っていうんですかね。一般的にはどうなっているんだろうっていう研究がまず第一に必要かなと思っています。例えば、本当にドキドキしている呼吸感だとかをある程度項目としてロジックとして挙げられるとは思うんです。でも恐らくそれ以上のことを人間はやっているんだろうなというのを感じています。最近はいろいろとそういったところを、ある意味どうわかりやすく作ろうかなということを考えている中で、やっぱり人間って難しいな、表現するのは難しいなっていう壁にちょっとぶち当たってるところです。
(南澤)確かにif文で書いたら負けですよね、明らかに。
(晃之)そうですね。if文でこれっていうふうになっちゃうと、ちょっとパターンが見えてしまったりだとかするので。
(南澤)そうじゃなくて、ちょっとある状態を、例えば世界観みたいな場として用意しておいて、そこに対して、そういうパラメータ、新しい相手の、コミュニケーションのパラメータが入ってきたときに、どういう所作を生むかっていう、世界観の設計のような話になってくるから、確かに難しいですね。
(晃之)難しいですね。もうこれは、やっぱりどうしても、また観察して、実際の女の子がどういう行動を取るのか、実際女の子にずっとカメラつけてその生態を観察できればいいんですけど、さすがにそういうのはちょっと難しいので。そこはある程度、こうであってほしいっていう、自分たちの欲望っていうか、相手の欲求の部分に立つときも、それが不自然にならないように、実際にある人間を見て、自分たちで解釈して、少しわかりやすく表現する。要は一般的な人たちに、わかりやすく表現することが、私たちアーティストの仕事かなというのも思ってる部分があります。その難しいところを、どう解釈していくのかっていうところで、今後ともそういった動きに関してこれから突き詰めていかなきゃいけない部分があって、やっていきたいなって思っています。
SayaがMiss iD 2018 Auditionに出場した時の映像。「ミスiD2018 ぼっちが、世界を変える。賞」を受賞した
触れ合わない信頼感を作ることができれば、
バーチャルなキャラクターも市民権を得られるのではないか
(南澤)仲谷さんが前、エモーショナル・リアリティっていうのをおっしゃっていたと思うんですが、感情と情動とそのリアリティっていうところって、今後どういうふうに何をやっていけば、今言っていたような、こういう所作のデザインだったりなどの表現をできるように持っていけると思いますか。
(仲谷)月並みのことと、よくわからないことを、これから言います。
(南澤)はい(笑)。
(仲谷)月並みのことを言うと、バーチャルリアリティで利用できる技術も確立し始めて、コンピューターグラフィックスによる表現もこれだけ高精細で美しいものになってきたので、あと加えるとしたら、触覚的な内容(=触感なるもの)だとは思っています。触覚的なものの中で、実際に触れられるものがいいのか、温度や気配のようなふんわりと感じられるものがいいのかを、エモーショナル・リアリティと言い始めていた時期に考えてはいました。それから、1年ほど考えてみて、実際に触れられるということは、とても重要なのですけれど、狭義の皮膚感覚だけでなく身体の感覚そのものを、うまく捉えらてみたいと思いました。自分の身体が相手と向き合ったときに、どのように変化をするのかの「気づき」だったり、呼吸の様子が何となく変わるとか、そういった感覚を、多分、何となしに皆さん、感じているのではないかなと思います。そのあまりうまく言葉にできない感覚を、アーティストの方は表現として明示的に体験者に提供することができるのですが、その体験をサイエンスの道具立てを利用して解析して、その要素を一個でも見つけることができたら、エモーショナル・リアリティをデザインする、現実感に実在感を加えるというようなことができるんじゃないかなというふうに感じています。ただ、具体的な方法は、わかりません。
(南澤)でも、仲谷さんとテクタイルで活動をさせていただいたときに、ダンサーさんと一緒にワークショップをやったことがあって、そうすると、本当にお互いの背中を触らずに、相手の背中をこう、腹を見るとか、それをするだけで、実は見られた人の動きが柔らかくなる。可動域が実際増えたりするんですよ。メカニズムとしていろいろ解釈しようとすると、多分、意識の向け方だったりとか、緊張の向け方だったりとかが変わるんだなと思うんですが、実際、そこに接触はない。何の触れ合いもないんだけれども、やっぱりそこで何か、2人の間でインタラクションが発生していて、それによって体への変化が起こる。僕もそのときに、すごく、やっぱり触覚ってただ触るというだけじゃない。触れ合ってないけれど、皮膚感覚的なやり取りっていうのは発生してるし、特に向き合ってるときとかに相手に緊張感を感じる瞬間っていうのが、まさにそういうことなはずで、そこに踏み込むっていうのが、実はさっきもおっしゃってたところで、Sayaも次のステップをさらに考えていったときに、「触れ合わない触覚」というところに踏み込めると非常にいいなと。
エモーションとHaptic Designっていうのが今回のテーマなんですけど、やっぱりいろんなところで、触覚的とは伝えられますかって話は出るんですけど、何かぶるぶる震えていても、一応、そこにラベルを貼っていくってことで、怒っているっぽい、楽しんでいるっぽいっていうのは何となく納得感がそこにいくものの、それも普段のこういうコミュニケーションとはまたちょっと違う言語になっている気がしていて。普段のこういう向かい合ってるコミュニケーションでの触覚って、どちらかというと、間にあるんですよね、この辺にある、場とその力と、相手の心拍とかをきっと何らかのかたちで、感じ取ってるなというところで、(Sayaさんでも)見られると面白いなって思うんですが、どうしましょうね。
(友香 )(笑)
(南澤)でもあんまり、この領域は取り組まれていないような気がするんです。触覚っていうとやっぱり触ったりで、ビジョンって言っちゃうと、画像処理になっちゃうし。でも何か気配とか、何となく間にあるような、エーテルというんですかね、空間の中にエーテルが漂っている、それが人間間を繋いでいるみたいな、そういう感覚ももしかするとあるのかもしれないと。
(晃之)日本人ならではの感覚というか、結構、相手を察するっていう感じですよね。ツーカーの仲じゃないですけど、相手をどう思うとか、思いやりの心だったり、そういったところの部分も、Sayaにも相手をどう思っているのかなっていうことを考えさせるっていう行動がまず、必要になってくるのかなっていう気はしますね。
(友香)そうすると私たちは、Sayaはパーソナルスペースを唯一侵して人間の心に入り込みやすい存在になれるんじゃないかなって思ってるんですよね。そういう、想像みたいな信頼感、触れ合わない信頼感を作ることができれば、バーチャルなキャラクターも市民権を得るステージってあるのかなっていうふうに感じてます。
(晃之)非常に大きな宿題をいただいたような感じがします。
(一同)(笑)

この子がいるから大丈夫だという信頼感を
いかにしてつくりだすか
(友香)自分だけをずっと見続けているかわいいキャラクターが、パーソナルスペースにずっといるって、すごく自分にとって心強いなと。私、VRで、一回飛行機に乗って、弾を撃って敵を倒すという体験をやったことがあるんですけど、ちょっと怖かったんですね。そのときに、女の子のキャラクターが、ずっとそばにいてくれて、あそこに敵がいるとか、いろいろ言ってくれるんですよ。それがすごく頼もしいというか、この子がいるから自分は大丈夫だと、敵に撃たれて死なないみたいな、何か安心感があって。どうすればSayaに対してもそういう信頼感を感じてもらうことができるかと考えたことがありました。
(仲谷)Sayaに心を見透かされてるなって感じるときはないですか。
(友香・晃之)(笑)
(晃之)どうなんだろう。どっちかっていうと、こっちが作らされている?
(友香)今日、メイキングの動画は撮らないでねって言ってたのは、やっぱりSayaが女の子だったら、自分の生首とか素肌とか撮られてほしくないはずなんですよ、というのがあって。
自分たちも、あんまりSayaに気持ちを入れ込むのをやめようって思ってた時期があったんですね。やっぱりネガティブな声が聞こえてきたりすると、自分が親な気持ちになってすごく落ち込むので。でもやっぱりそうはいかないんですよね、作ってると。なので、そういう作者側も、結局ピュグマリオンじゃないですけども、そこまで入り込んでしまうときっていうのはあります。
(晃之)そういう意味では作らされてるような。
(友香)作らされてますね。Sayaにね。すごくね。
(晃之)そういうふうに感じます。
(南澤 )そのときの体の感覚ってどうなってるのでしょうね。没頭しているフローみたいな感覚になっているのか、それとも幽体離脱じゃないですけど、ふわーっとした感じになってるんでしょうか?
(友香)どうなんでしょうか。その不気味の谷を越えるポイントってどこなんだろうって、どうやって作ってるのかって、みんな、やっぱりすごく知りたがっていて、でも私たちは何とも言葉にできないんですよね。どうなんですかね(笑)。
(晃之)ただ黙々と。
(友香)でも、そこは解明していかないといけないと思ってるところなんですよ。人によっても不気味の谷のポイントは違いますし、彼女を受け入れるポイントも変わってきますから。
(南澤)何かまた、生命感とか存在感とかをどういうふうに作って、僕らはSayaみたいな存在とコミュニケーションをしてけばいんだろうっていうところに関して、ちょっとじっくり考えていきたいですね。というわけで、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。仲谷先生とtelyuka さん、ありがとうございました。
ゲスト

石川晃之 / 石川友香(TELYUKA )
2011年頃から、夫婦で3DCG制作を行うユニット「TELYUKA(テルユカ)」というアーティスト名で活動を開始。GarateaCircus株式会社代表。2人ともCGゼネラリストアーティストとして、ムービーの制作やキャラクターアセット制作の依頼を請負っており現在はVritualHumanProjectsを中心にオリジナルヴァーチャルヒューマンから、実在する・していた人間の制作を行う。制作に関しては、友香がディレクションを、晃之(てるゆき)が技術面を担当し制作を行う。

仲谷正史(慶應義塾大学 環境情報学部 准教授/JSTさきがけ 研究員)
学生時代より人間の触知覚研究に携わる。これまでに新しい触覚の錯覚の発見を通して触感の不思議を解明する研究や、やさしく触れた時に反応する身体の触覚センサ:メルケル細胞の機能を明らかにする研究に従事。共著書に『触楽入門』(朝日出版社)、『触感をつくる――《テクタイル》という考え方』(岩波科学ライブラリー)。
ホスト

南澤孝太(みなみざわ・こうた)
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD) 准教授。2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻博士課程修了、博士(情報理工学)。 触覚を活用し身体的経験を伝える触覚メディア・身体性メディアの研究を行い、SIGGRAPH Emerging Technologiesなどにおける研究発表、テクタイルの活動を通じた触覚技術の普及展開、産学連携による身体性メディアの社会実装を推進。 日本バーチャルリアリティ学会理事、超人スポーツ協会理事/事務局長、JST ACCELプログラムマネージャー補佐を兼務。
※肩書は登壇当時のものです。
TEXT BY ARIA SHIMBO