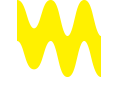2017.11.04
触覚と社会はどう結びつくのか?
Haptic ×(Social)Designの実践手法を語る(前編)
〜ゲスト:渡邊 淳司、太刀川 英輔/ホスト:南澤 孝太〜
“わざ”にフォーカスし、Haptic(触覚)の研究やデザインに携わる方々をゲストに開催するシリーズイベント「Haptic Design Meetup」。2017/11/4に実施したVol.5は「Haptic ×(Social)Design」をテーマに行いました。
イベントのオーガナイザーである南澤 孝太氏をホストに、渡邊 淳司先生(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)、太刀川 英輔さん(NOSIGNER)を交えて行われたクロストークの模様をお届けします。
※肩書は2017年11月4日登壇当時のものです。

ー左から南澤 孝太氏、太刀川 英輔氏、渡邊 淳司氏
自身の体験をベースに
触覚のデザインを行う
(太刀川)よろしくお願いします。NOSIGNERというデザイン事務所をやっています太刀川です。今日呼んでいただいた淳司さんとか南澤さんとは、結構古い付き合いで、もう10年ぐらいたちますかね?

(南澤)実は、「TECHTILE」というプロジェクトが、このHaptic Designの前身としてあるんですけど。仲谷さんと筧さんと太刀川さんの3人が始めて。その当時、最初に展示会をやったときに、太刀川さんに「20~30万円で会場をつくってくれないか」っていうお願いをして……。
(太刀川)TECHTILEの、1年目、2年目、3年目の会場構成をしたんですけど、そのときの会場構成が世界ベスト5のエキシビション&リテール、要するにショップのインテリアということになっちゃったんですよね、錬金術。
(南澤)アルミホイルで、ワークショップに参加してもらった人たちに町の中のテクスチャーを取ってそれを会場に貼っていくっていうことをしましたね。
(太刀川)懐かしい。とにかくそういうことでお付き合いが長く、淳司さんも、僕がNOSIGNERを始めて間もなくぐらいのころにコラボレーションさせていただいたりしていて。久しぶりにお二人と話すのをすごく楽しみにしていました。
僕は普段グラフィックや空間のデザインをしています。僕はデザインってものすごく可能性のあるものだと思っていて、その可能性を最大化させたいと思っています。だから、今、デザインが入っていない領域に対してデザインを適用すると、いかにその変化を加速させることができるかっていうのを僕が生きてる間に200~300個はデザインによって世の中が少し変化したかもっていうケーススタディをつくりたいと思っています。それのうちの、例えば防災のデザイン。この本なんかは持ってる人もいるかもしれませんね。

東京都が都内の各家庭に配布した。750万部発行された防災ブック
(太刀川)東京に住んでる方なら知ってる方が多いかもしれませんね。そういう防災とか伝統産業とか科学技術とか、あとはコミュニティビルディングとか、そういう割とソーシャルなテーマのデザインをずっとやっているデザイナーです。
(南澤)ありがとうございます。渡邊淳司さんのほうからもお願いしたいと思います。
(渡邊)こんにちは、渡邊です。よろしくお願いいたします。僕は、もともとはバーチャルリアリティの研究室、舘 暲先生の研究室出身で、南澤さんとも同じ研究室でした。そこで、人間の知覚とテクノロジー、人間の知覚特性をインターフェイス技術に活かす研究をしてきました。それを、科学館や美術館でたくさんの人に体験してもらうということをやってきました。

僕と触覚の関わりでいうと、2年ちょっと前に出した『情報を生み出す触覚の知性』という本があります。この本で、触覚について書いていると、だんだん、「僕、実は触覚に興味がないんじゃないかな」と思い始めまして。触覚自体というよりも、触覚と情報とか、触覚とコミュニケーションとか、触覚を使って、どうやって人と人の間に新しい価値をつくるかということに興味があるのかなと思っています。
あと、僕がいつも自己紹介するときには、心臓を人にお渡しすることから始めます。「心臓ピクニック」というワークショップを続けていまして。太刀川さん、この振動する箱を持ってもらえますか? 緊張してるのがばれるかもしれません。
聴診器を胸に当てると心臓の鼓動が白いボックスを通じて振動として再現される
(太刀川)今、すごい緊張してるかもしれないですね。
(渡邊)だいぶん速いですよね。
(太刀川)だいぶん速いですよね。何かすごい、生な感じしますね。
(渡邊)「心臓ピクニック」のワークショップでは、心臓ボックスと言いますが、鼓動に同期して振動する白い箱を持って外を歩いたり、寝たり。自分の心臓の鼓動の変化を感じたりすると。例えば、子供同士が触れ合ったりとか家族でいろいろ触れ合う。そのときに気をつけてきたことは、触れるという感覚に手順を踏んで意味付けをしていくってことなんですね。触覚っていっても、ただ触れるだけでなく、それに意味を見出す過程がすごい重要です。
最初に、まず自分の心臓ボックスを触ってみる。それで、「あっ、本当にあるんだ」っていうことを感じて、相手に触れると、「ああ、この人にも、ちょっと違うけどあるんだ」ということを認識する。自分が走ったりすると、だんだん速くなってる自分を感じたり。さらに、この装置は記録ができるので、記録して置いてみる。僕がいなくなってもドキドキしてると。それで、急に止まったりすると、「あっ、渡邊くん、大丈夫かな?」と思ったりするわけです。あと、記録したあと、電源を引っこ抜くとすごい切ない気がするんです。触感に対して、僕らは生命みたいなことを意味の上書きをしているわけです。
もう1つ話をすると、「触り言葉」をつくろうっていうことをやってきました。触覚のコミュニケーションデザインですね。公衆電話を使って振動をお互いに送りあうという。新しい公衆電話の使い方はないんだろうかと考えたわけですね(笑)。
触覚でコミュニケーションを行うことができる公衆電話
体験者がお腹と背中に振動子の付いたベルトを付けて、公衆電話の9個のボタンに違う触感を割り当ててあげて、ボタンを押すと相手に、「ズキューン」、「パァーン」、「ゴゴゴッ」とか、「グサッ」とか触感だけでコミュニケーションをするシステムをつくってみました。普段、スマホでは音声もしくは映像で感情のやりとりをするんですけれども、この場合、触感だけでやりとりをする。LINEとかでスタンプだけでやりとりする方がいらっしゃると思いますけれども、それに近い感じですね。
(南澤)ありがとうございました。いわゆる触覚まわりの研究は文字によるコミュニケーションとは、違うお話が聞けるというふうに皆さん感じられているかなと思います。僕自身も、触覚のテクノロジーはずっとやってきているんですがしばらくして気づいたのが、一生懸命、震える、触るとか握るとかいう感覚っていうのを技術で再現しようとしていても、実際の触感との違いが生まれるんですよね。そうしたときに、もっと実は大事なものってあるんじゃないかと。太刀川さんいかがでしょうか。
時代とともに移り変わる人が好む素材感を
どのようにとらえるか
(太刀川)まだ今回のテーマであるソーシャルと触覚ってのが割とジャンプがあって、行ったり来たりしちゃうと思うので、まずは、デザインにおいて、テクスチャーとは、触覚とは何かって話からしたいなと思います。
皆さん、ちょっと目を閉じておしゃれなカフェを想像してほしいんですね。例えばなんですけど、そのおしゃれなカフェにプラスチックありましたか?ないような気がするんですよ。ガラスとか木とか鉄とか革とか布とか、こういったものばっかりになってません?このことって僕は、デザインにおいてすごく面白い変化が起こってると思っていて、要するに、ちょっと前までデザインって思われていたところで使われている、われわれが気持ちいいと思う素材と、今、気持ちいいと思う素材の時代が全く違うんですね。今言ったような素材は、すごくザックリ言うと、工業化のちょい手前の素材なんですよ。要するに、人類史において僕らが慣れ親しんでいた素材です。でも、最近50年ぐらい、いろんな素材が出てきていて、それは化繊とかもそうだし、プラスチックもそうだし、何か金属でもかなりピカピカのクロムメッキとか、そういったものに対してわれわれは何か懐疑的な視線をいつの間にか持つようになっていることがあるんですね。
それを見分ける手掛かりが、触覚だったりするんですよ、デザイナーは、当然どういう質感であるべきかを決める仕事をする人なんで、例えば具体例をいうと、グロッシーなピカピカした素材よりも、マットな素材のほうが、最近かっこいいものってすごい多くないですか。それは、要するに工業製品に見えにくいというか、そこに手がかかっているはずだとか、その素材がそのまま感じられるように、少なくともテクスチャーがコントロールされている。
でも一方で起こってるのは、ものすごいたくさんの記号が世の中に満ち溢れていて情報過多なので、デザインの収まりというか、ディテールとしては、量を少なくしたいんですよね。要するに、造形的な情報は要らないけど、触覚的、物質的情報はほしいっていう時代になってきてるってことをすごく感じています。
あと、さっき震災の話があったんで、震災の話を少しだけします。twitter上の有名人の津田大介さんのオフィスを設計したときに、天井にもともと家だった木の残骸を使いました。要するに情報が完全に宿った、物証としての物質がそこにあると。津田さんって、東北震災の時に現場を渡り歩きながら、東北の社会起業家とかとつながりながら、それを発信してくださったメディア・アクティビストなんです。このオフィスを見て分かるのは、かなりラフですよね。完成品はラフじゃないんですよ。だけど、未完成な状態に戻ったり、破壊されたあとって、ものすごくラフだし、あるいは素材の段階ではラフじゃないものはないんですよね。

津田さんのオフィス。天井には岩手の震災瓦礫が使用されている
(南澤)原始に帰った感じと一緒ですか。
(太刀川)そうなんです。この素材の粗さというのがものすごくあらわになったのが、またそういう災害の体験でもあって。結構僕らは割と表層の世界に生きてるわけですよ。アスファルトだって、何十センチしかないし、それが全部はげると、そこの裏には土があるんだけど。しかもそれがアスファルトだと思ってたら、それに全部亀裂が入ってみるとすげえ邪魔な岩がいっぱい転がってるってことがあるし。だから、その裏にある物性があらわになるときに、それはラフになっていくっていう、その粒度が変わっていく感じは、何か当たり前の現象なんだけど、ひょっとしたらさっきのツルツルしたものよりもザラザラしたものを信頼しているという僕らの感覚にひょっとしたら近いのかもしれなくて。そういうことは、震災のときは結構生々しいところへいっぱい行ったんで、考えましたね。出来上がった建築、それはある意味では力がないんですよね。あらわになってるのが少ないから。でも、テクスチャーというか、その物性そのものがあらわになっていくようなデザインをすると、多分、その奥にある素材性に触れることができる。その導入をデザインでできるかもしれないっていうのは面白いですね。
(南澤)天井なんて、直接もちろん触れるわけじゃないんだけども、手触り感としての情報量がものすごく多い気はしますね。写真見てるだけでも、すごくその手触り感が想起されるような感覚がしますね。
(太刀川)本当、そうだね。
(南澤)だから多分表面をフラットにしちゃうってことは、ある意味情報量をミニマムにしようとする行為だと思うんだけれども、逆に手触り感が創発されるような情報を与えてる。その空間に配置することで、そこに多分立ってるだけで、その質感ってのをきっと感じとるんだろうなっていうよう気がします。淳司さんいかがですか。
空間デザインにおける
Haptic Design の考え方とは
(渡邊)建築は人が必ず中に入るじゃないですか。それで人が動く中で空間のテクスチャーがどう変わっていくかとかをデザインされてる方は考えているのかなと思っていて。そのときに、例えば最初、TECHTILEの会場をデザインしたときには、なぜその素材を使ったのかとか。もう少し聞きたいですね。
(太刀川)TECHTILEの一番最初の年はサランラップを1万メートル圧着して素材をつくって、それで氷の柱みたいなのをつくってましたね。
(南澤)あれ、すごく最初衝撃を受けました。
(太刀川)あれは、めちゃ安かった。学生あがりぐらいだよね。
(南澤)この空間は、ものすごい手触り感なんですよ。
(太刀川)このときに考えていたことは、もちろん1つ目がスーパーローコストでしょう。超ローコストだから、いわゆる建築建材的な質感のものが、物理的にも使えないし。その素材感ということをテーマにしたときに、それをどう空間化できるのかというと、実は建材じゃないほうが有利だと思ったんですよね。そういう質感を与えるような何かって何だろうっていうことをいっぱい考えたりしながら。2年目は泡だったんですよね。これは触覚的に見えるんだけど、触覚はほとんどないものなんですけどね。
(渡邊)例えばこういうパブリックな場とか、知らない人同士が現れる場において、テクスチャーというものはどう考えるべきだと思いますか?
(太刀川)テクスチャーって世の中にものすごくいっぱいあるんですよね。この部屋にももうほとんど数え切ることができないくらいのテクスチャーがあるわけです。一方、デザインって、ものすごく運べる情報が少ないんですね。なので、1種類のテクスチャー的な表現だけでその空間を支配すると、ものすごく何をしたって触覚的な空間になるんですよ。ものすごくザラザラした、ものすごくツルツルした空間。そのときに空間全体がある方向性を持つじゃないですか。その方向性をどういうふうに設計するのが良いのかなっていうのを毎回考えてた気がします。情報として伝えられる量が少ない代わりに、伝わったときはめちゃ強いってことが、デザインっていうコミュニケーションの強さなので。
特に3年目は僕、空間的にうまくいったと思っているんですけど、そういうことを考え、触れ、つくる間にも、その展示体験というか、TECHTILEというその触覚と技術とか、触覚体験を考える・感じるっていうことを空間化するっていうテーマの中で考えていく中で、お金がないから、ボランティアをいっぱい募集するでしょう。この人たちっていうのは、当然展示にも来るお客さんでもあるわけですよ。この人たちに、ただ「手伝ってよ」って言っても、なかなかみんな手伝ってくれないから、触覚のワークショップをします。1メーターかけ1メーターのアルミホイルを全員に持ってもらったんですよ。で、街に出てもらった。要するに、それで街にあるそのテクスチャーを取ってきてもらったんですよ。

TECHTILE #3では、会場がアルミニウム箔に写し取られた200以上の東京の街のテクスチャーで埋め尽くされた
(太刀川)懐かしいね、これ。例えばこのとき、ピアノの鍵盤を取ってる人とか。いろんな街中にあるテクスチャーをそのまま空間化する。アルミホイルってすごくいい素材で、僕ら視覚と触覚と両方に触れてるんだけど、アルミをこするときっていうのは、もう触覚しか意識してないんですよ。ひたすら触ってたなあ。
(渡邊)見た目を銀に統一すると、逆に触覚にフォーカスできそうですよね。
(南澤)さっきの、空間のいろんな触感なくして1つにするってのと同様に、視覚的にももう全部ミニマムにしてしまって、本当にそこにフォーカスする。意識を集中すると。
(渡邊)これ、人によって何を選ぶのか、結構違いますか。
(太刀川)もう全然違うんですよね。だから、土っぽいものを選ぶ人もいるし、凸凹の丸を選ぶ人もいるし。あとは、意外とテクスチャーだけにすることによって、マンホールの文字とかも正確に覚えるっていうか。「こんなことがこんなところにも彫り込まれてたんだ」みたいなことを、要するに街の触覚空間を体験するっていうことをワークショップ化して、ワークショップの参加者にそのままこの空間を演出することを手伝ってもらったっていう。
いろいろなものが条件として足りないということを逆手にとって、もうそのプロセス全体を触覚技術体験にしちゃおうみたいなことが根底にあるコンセプトだったんですよね。
(南澤)それによって参加したい人たちがもう無意識的にというか、その触れるっていう行為にものすごく意識を向けるようになって。参加したあとの人たちが、もうとにかく、これ、終わったあとでもいろんなものを見て、「あれを写し取ればいいんじゃねえか」って、みんなずっと思いながらしばらく生活するっていうモードに入るんですよね。
(渡邊)やっぱり個人にとって、その環境のテクスチャーを全部身体化していく活動が、すごい面白いなと思います。触れたことで、それぞれ違うものの見方をしてるとか、違う感じ方をしていることが実感できる。次にソーシャルという文脈に引き寄せたとすると、どういうふうにそこから社会の問題を解決していくのか、一緒に考えられるのか、と思ったりします。
中編に続きます。

渡邊淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 感覚表現研究グループ 主任研究員)
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 主任研究員(特別研究員)/東京工業大学工学院特任准教授兼任。博士(情報理工学)。人間の触覚の知覚メカニズム、感覚を表現する言葉の研究を行う。人間の知覚特性を利用したインタフェース技術を開発、展示公開するなかで、人間の感覚と環境との関係性を理論と応用の両面から研究している。近年は、学会活動だけでなく、出版活動や、科学館や芸術祭において数多くの展示を行う。主著に『情報を生み出す触覚の知性』(毎日出版文化賞(自然科学部門)受賞)がある。

太刀川英輔(NOSIGNER代表 / 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特別招聘准教授)
ソーシャルデザインイノベーションを目指し、総合的なデザイン戦略を手がける。建築・グラフィック・プロダクト等への見識を活かした手法は世界的に評価されており、国内外の主要なデザイン賞にて50以上の受賞を誇る。東日本大震災の40時間後に、災害時に役立つデザインを共有するWIKI『OLIVE』を立ち上げ、災害時のオープンデザインを世界に広めた。その活動が後に東京都が780万部以上を発行した『東京防災』のアートディレクションへ発展する(電通と協働)。
ホスト

南澤孝太(みなみざわ・こうた)
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD) 准教授。2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻博士課程修了、博士(情報理工学)。 触覚を活用し身体的経験を伝える触覚メディア・身体性メディアの研究を行い、SIGGRAPH Emerging Technologiesなどにおける研究発表、テクタイルの活動を通じた触覚技術の普及展開、産学連携による身体性メディアの社会実装を推進。 日本バーチャルリアリティ学会理事、超人スポーツ協会理事/事務局長、JST ACCELプログラムマネージャー補佐を兼務。
※肩書は登壇当時のものです。
TEXT BY KAZUYA YANAGIHARA