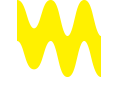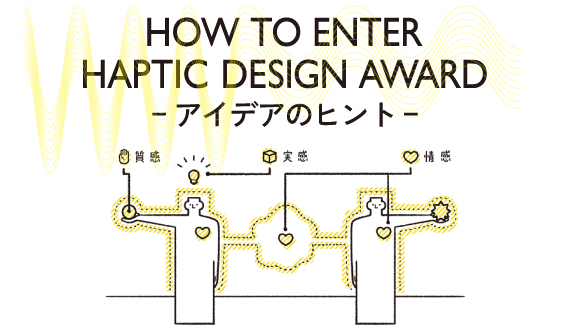2017.01.31
「HAPTIC DESIGN」は世の中をシームレスに。 “気持ち良さ”と“リズム”で考える、HAPTIC的ものづくり
〜ゲスト:渡邊淳司 、泉栄一、堀木俊/ホスト:南澤孝太〜
見る・聴くデザインから、“触れるデザイン”へ。ポスト・インターネット時代といわれる昨今、人々がリアリティやライブ感といった身体性を伴うコミュニケーションを求めるなか、にわかに注目を集める「HAPTIC」。
去る2016/12/10(土)、VRはもちろん、グラフィック、プロダクト、UXなどさまざな分野に可能性を秘めた、この「HAPTIC」とデザインの融合を目指すイベント「HAPTIC DESIGN CAMP2」が開催されました。
今回はそのなかで、“自然体”や“着心地”を重視されるファッションブランド「MINOTAUR」の泉栄一氏と、空間としての“気持ち良さ”をモットーに設計を行う建築家の堀木俊氏、人の知覚研究やその特性を活かしたインタフェース開発を行う研究者の渡邊淳司氏というフロントランナー3人をお招きし、各々の分野の“デザイン”に隣接する「HAPTIC DESIGN」を語っていただきました。聞き手は前回同様、南澤孝太氏がお届けします。
設計において何より重視するのは「気持ち良さ」

ー隈研吾建築都市設計事務所 堀木俊氏
(南澤)堀木さんは「デザインや建築の本質は、極小から極大へ」とおっしゃっていて(参照記事)、関わられているプロジェクトでも、さまざまなスケールの設計をされているなと思いました。例えばプロダクトでは素材である木の触り心地などミクロなテクスチャー、都市設計では曲がり角の多い道はざらざらしているなど街を歩いていて身体で感じるマクロなテクスチャー、いろんなスケールのお仕事に携わられててますよね。指で触れる触覚的なものと、身体全体で感じる部分は、意識的につなげて設計しているのですか?
(堀木)実際まとめてみたときに初めてそういうつながりに気づいて、自分でも発見でした。僕は、図面をパターンだと思っています。縮尺された図面のパターンが気持ちのいいリズムになると、空間としても気持ち良い気がして。何に対しても“気持ち良い”設計を意識しています。
(南澤)建築にはテクスチャー感というか、「触ったら気持ちいいんだろうな」と思うものがありますね。実際のスケールではもっと大きいので触る対象ではなくなると思うですが、堀木さんは建築の模型の段階で気持ち良さを考えるのですか?
(堀木)模型だけでなく、打ち合わせでいろんな情報をまとめて、クライアントに設計の意図を説明するんですが、一番わかりやすい反応は「気持ち悪い」という言葉。「カッコ悪い」は好みだけど、「気持ち悪い」は根源的な気持ちだから、すごくディスられた気がしますね(笑)。
(一同)笑。
(堀木)逆に、クライアントに「気持ち良いね」と言われた時には、相手が偉い人だろうが新人だろうが「いいじゃん!」って思う(笑)。例えば最終的に図面上で、数字や記号になっていたとしても、そこにたどり着くまでには、互いが感じる「気持ち良さ」をなるべく言語化・現実化するようにしています。言葉に表すのは難しいんですけど、不協和音をなくして気持ち良いリズムにしていくのが打ち合わせだから、気持ちが良い悪いって、やっぱりとても大事ですよね。
天井や床は実際に手では触らないですが、空間にいると人は何かを感じ取りますからね。「HAPTIC」においても視覚は重要だと思いますが、我々は視覚にかなり重きを置いて設計をしていて、その「気持ち良さ」を判断する努力をすごくしていますね。

ーNTTコミュニケーション科学基礎研究所 渡邊淳司氏
(渡邊)堀木さんの話を聞いてて思ったのは、テクスチャーをデザインした家はクセになるだろうなと思いました。ゾワッとしながらいつまでも触っていたい、とか……僕だけですかね?(笑)
愛情というのはパターンを繰り返し、その対象と関わりを持ち、それを繰り返すことで対象に対してだんだん心が移っていく過程なのだと思っています。
(南澤)堀木さんが「気持ちいいと感じるリズムを打ち合わせで探る」と言っていましたが、理解やテクスチャーというのはリズムだから、シンクロさせやすいのかもしれないですね。そして気持ち良いリズムを継続すると、どんどんくせになって愛情になっていく、と。
(渡邊)触れて相手をスキャンするうちに自分の中にパターンが生まれていく。それは身体的なことなので、結果的に心を動かすものになるのだろうと思います。
服は、人と環境をつなぐインターフェース

ーMINOTAUR 泉 栄一氏
(南澤)泉さんの服づくりの話を聞いていると、着心地を感じさせない工夫はしているけど単にゼロにするのではなく、むしろちょっと違和感を与えて、着ている人の快適さを生み出そうとされている、と感じました(参照記事)。具体的に、どうやってデザインを行っているのですか?
(泉)僕が服作りを通じて、もっとも注意しているのは、気持ち良さや伝える内容のバランスです。僕は、皆さんの頭の中のイメージをちょっとだけ超えてくる感じ、ちょっとした違和感、そういった感覚を大事にしています。イメージと大幅にずれていたら気持ち悪く、想定内だと驚きがない。また洋服をつくるとき、同時に「どう気づいてもらうか」「どう意識させるか」を考えています。それは服のデザインだけでなく、パッケージであったりコピーライティングであったり、いろんなことと連携していかなければいけません。やはり服のデザインだけで新しいことをやるのは難しい。

ーMINOTAURのスマートフォンでコントロールできるヒーター内蔵のジャケットやアウターを扱うプロダクトライン「I/O COLLECTION」
(泉)言うなれば、意識を誘導するデザインを行っているんです。例えば、普通なら自分のブランドのロゴを入れる場所に、みんなが共通認識を持っているピクトグラムを入れるとか。アウトドアの機能を気づいてもらえるように意図的にアウトドア的な素材を使ってデザインしたり。ある程度一般的に認識がある範囲を混ぜて、新しいことをやっています。なぜならみんなが基本的に知っていることを入れないとコミュニケーションが始まらないし、そこに意識が向かないと思うので。
(渡邊)泉さんが考えるオシャレとは、どのような状態を言うのでしょうか?
(泉)デザイナーさんによって定義はさまざまですが、僕の思うオシャレは「自然体」だと思っています。その人の自然体な魅力を引き出すこと。それを洋服でどうサポートするか、というのが僕の考え方ですね。
少し前に、デニムそっくりに見えるスウェットが流行りましたよね。あれも初めは、デニム好きから大きな反発がありました。
でも実際に履いてみたら、着心地がいいと気付くんです。僕は、デニムなどの伝統的な素材に対して、礼賛でもアンチでもありません。両方の良さをうまくまとめられる、落とし所をいつも探しています。
(渡邊)MINOTAURは、外に向けては見た目を担っていて、内側に向けては心地良さを持っている。つまり内側には柔らかさなど、触感という機能を提供しながら、外側にはしっかりした印象が出ているところが興味深いと感じました。そのあたりの設計指針があれば教えてほしいです。
(泉)着心地が良いだけを追求するなら、きっとみなさん寝間着になってしまいますが、寝るときの格好で人に会ったら失礼があったり、着すぎて布がへたってしまっていて、他者からの印象がルーズになる。快適さばかりに走るとルーズになりがちなので、そこを僕の仕事が解決してあげられたらいいなと思っています。

ー慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 南澤孝太氏
(南澤)ちなみに堀木さんだったらどういう風に、身にまとうものをデザインしますか?
(堀木)ルーズなものになりそうですね、僕自身ルーズだから(笑)。例えば、風に揺れる服とか。風が吹くと服が流れるのは、感覚的にも気持ち良いし気軽なんじゃないでしょうか。洋服のカタチが変化したり、ずっと一定じゃないほうが、気持ちいいんじゃないかなと。
(南澤)例えば、外を歩いていて風が吹くと自分の肌感覚が変わりますが、泉さんの視点では、服を着ている人という存在と、周りの空間の間をデザインすることは考えていますか?
(泉)それは服のデザインそのものと同じくらい考えています。場所と人の間、このシチュエーションでなければ合わないという服もありますから。シチュエーションに合う・合わないは昔ほど厳密でなくなりましたが、現代社会は生活がスピードアップしているので、シチュエーションは分かれているんだけど、真面目な場でも自然体でも、またいで対応する必要が出てきました。理想としては、無理やり合わせるんじゃなくて、どんな場所でも自然に対応できる服。僕らがどう努力すれば、どんなシチュエーションでも快適に過ごせるんだろう、ということを考えています。
(南澤)なるほど。エンジニアリング用語でいうと「インピーダンスマッチング※」ですね。自分のメディアデザインの仕事でも、二つの要素をつなぐ必要があった際、その間をいかに滑らかにつなぐかを考えます。同じ弾性でつなぐとか、同じ硬さのもの同士ならくっつくとか考えたときに、皮膚って自分自身の存在と環境との間のインターフェースであると捉えられるんですね。ファッションのお話を伺っていると、まさに人間の皮膚の上にもう一枚レイヤーをかぶせてやることによって、外の世界によりフィットするようにつないであげる役目があるのかなと。
渡邊さんは、人の感情や、人と人の関係性をどう繋げられるか、人間の境界とその先の設計をされています。自分とファッションと、さらにそこに他者が入ったときにどんな設計ができると思いますか?
(渡邊)先日「TOKYO DESIGN WEEK」で、自分の心臓と同じ鼓動を打つ物体を自分の手で持つ、というワークショップを行いました。心臓って、自分の身体の中にあるけど、当然触ったことはないですよね。普段、自分の中にあるもの(心臓)が外に出てきて、それに触ると人はびっくりする。ここまでが第一段階。

ーNTTコミュニケーション科学基礎研究所 渡邊淳司氏提供(心臓ピクニック Heartbeat picnic @21_21 DESIGN SIGHT)
次に自分の心臓を「どうぞ」と他者に渡すんですね。すると渡された人も、自分と同じものが他者にもあるんだ、ということに実感を持って気づく。自分の内側に潜る、つまり自分への理解を深くすることが、のちに他者への理解につながるんだということが、このワークショップを通じてわかったことです。
ということを、泉さんのお話を聞きながら思い出したんですが、ファッションとして、服の内側の触覚を考えることは、自分の心が感じることを理解する試みで、それを意識するようになるということは、普段でも、他人が感じていることを想像する癖がつくようになるのかなと思いました。
※インピーダンスマッチング:おもに音響装置などで、特性の違う2つの装置・素材の間で効率良くエネルギー伝送を行うため、整合の取れていない接続部分を、不都合なくスムーズに伝えられるよう設計・調整すること。
「ものづくりを後世に伝える」
「触覚」の言語化と意味付け

(渡邊)堀木さんの発言で印象的だったのは「触れる公共」という表現(参照記事)。この言葉には単純に建築のスケールを大きくした以上の何かがある気がしていて、もう少し詳しく聞かせていただけますか。この「公共」の意味は、個人と個人のプライベートではなくパブリックっていう意味ですよね。公共に対して「触れる」というプライベートな行為で、どうやってたどり着くのかと思いました。
(堀木)建築の世界で、一番触れることを許されているのが職人さんです。今は職人と住み手が、分業化の中でかなり亀裂が深くなっている。言い換えれば分業のせいで触覚的でなくなった、と思っています。昔はふすまは自分たちで直せるなど、住み手もクリエイターだった。作る感覚と使う感覚が混ざっていくことで、ものと人の関係性が構築できるんじゃないかなと思います。
(南澤)触ることで、自分の体の一部になる感覚が得られるんですよね。家をつくる素材を触れながら作れば、自分が家に接続するというか、自分の一部になる感覚がある。触覚的でなくなって分断されたことで、自分のいる空間が分断されちゃったという。
(堀木)また、建築業界では職人が高齢化していることで、日本的なものづくりが途絶えてしまうという問題もあります。いま職人の感覚を後世に残していくために、触覚を保存してデータベース化できないかと考えているんですが、例えば職人と同じ感覚で紙をちぎることができれば、職人技を再現できるかもしれません。
(南澤)それは、おもしろいですね! 我々も、まずは「触覚」をいかに言葉や情報にするかを試行錯誤しています。「HAPTIC DESIGN」を考える前に、まずは触覚を共通言語にしていかないと、なかなか固有のノウハウの域を出ていかない。いかにノウハウや感覚的な部分を言語化して落とし込めるかが大切なんです。
(堀木)まだアイデア段階ですが「材料論理学」っていう学問があったらいいなと思っています。建築現場では、やはり職人がいちばん偉いんです。でも、棟梁は「何年も現場にいた、俺の言うことが絶対」とか言うんですが、間違っていることもけっこうあるんです(笑)。その棟梁たちの感覚をインタビューして、言語化して蓄積していければ、それを見ながら枠材は金属B、接着剤Cとか決めていける。共有の知識にしてプラットフォーム化することが必要ですよね。
(南澤)我々も「身体情報学」ができないかと思っていて。情報って常に一定なもののように捉えてしまいがちですけど、実は,受け取る人の状況や文化の違いによってその意味が変わります.それと同じように僕らが身体を通じて得る体験も,個々の身体の違いが影響するので,同じ状況や環境を再現したからといって同じ体験を得るとは限らない.この先人間がインターネットにつながっていろんなものが情報化していく中で、人々が体験を共有したり伝承したりできるようにするためには,人間の体感や体験をいかに情報化するか、というところで「身体情報学」ができたらいいなと思っています。まずは、体験を記号化したり情報化するところがスタートしていくんでしょうね。
(渡邊)「記号」と「情報」はたぶん違うもので、記号はパターンにできるけど、情報は人がそこにどういう価値や意味を見出すか、という話だと思います。0、1のパターンとして記録されてても、それを見た人間の中に新しいパターンが生まれる。そのパターンは身体性や考え方によっても違ってくるし、「ぞわぞわ」などの情動的なパターンは無意識のもの。こうした記号と情報は別物だと理解した上で、記号の世界と人の身体を介した世界は実は地続きで、人間はそこで初めて“本当の情報”を得るんじゃないかと思っています。

ー「HAPTIC DESIGN CAMP2」参加者との集合写真
ゲスト

渡邊淳司(わたなべ・じゅんじ)
1976年東京生まれ。NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 主任研究員/東京 工業大学大学院総合理工学研究科連携講座准教授兼任。情報理工学博士。視覚・触覚という人間の知覚メカニズムの研究を行い、その特性を利用したインタフェース技術を開発・展示するなか で、人間の感覚と環境との関係性を理論と応用の両面から研究している。近年は文化庁メディア芸術祭、ArsElectronica等の芸術祭においても数多くの展示を行う。

堀木俊(ほりき・しゅん)
隈研吾建築都市設計事務所一級築士。芝浦工業大学卒業 在学中スイス連邦工科大学ローザンヌ校に留学 2013年より隈研吾建築都市設計事務所勤務 プロダクトからマスタープランまでスケールを横断した様々な設計活動に従事する。 木材・繊維系素材などの基本素材をはじめ、新しい素材・素材の新しい使い方を見つける事を中心に設計活動を行っている。

泉栄一(いずみ・えいいち)
1990年からインポートファッション バイヤー兼デイレクターをつとめる傍ら、数々のイベントオーガナイズや選曲を勢力的に行う。インターナショナルな環境で培われた、ファッションカルチャーの表現の場として、2003年”font co.,ltd™設立。2004年よりファッションブランド『MINOTAUR』を本格始動。スマートフォン操作で温度が変わる服作りも話題を読んだ。ワコールのコンディショニングウェアー「CW-X」アドバイザー。スポーツウェアの技術と消臭テクノロジーを応用したエチケットブランド「MXP」メンズディレクター。「SONY」ショールーム、ストア、及び「JiNS MEME」のショップユニフォームデザイン。
ホスト

南澤孝太(みなみざわ・こうた)
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD) 准教授。2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻博士課程修了、博士(情報理工学)。 触覚を活用し身体的経験を伝える触覚メディア・身体性メディアの研究を行い、SIGGRAPH Emerging Technologies 等における研究発表、テクタイルの活動を通じた触覚技術の普及展開、産学連携による身体性メディアの社会実装を推進。 日本バーチャルリアリティ学会理事、超人スポーツ協会理事/事務局長、JST ACCELプログラムマネージャー補佐を兼務。
TEXT BY YUI TANAKA /EDITED BY MASARU YOKOTA(Camp)
PHOTOGRAPH BY HAJIME KATO