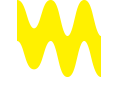2017.07.19
ボディイメージから紐解く「納得のいく身体」をデザインする方法
〜ゲスト:田中 由浩、倉澤 奈津子、竹腰 美夏/ホスト:南澤 孝太〜
“わざ”にフォーカスし、Haptic(触覚)の研究やデザインに携わる方々をゲストに開催するシリーズイベント「Haptic Design Meetup」。2017/7/19に実施したVol.2は「Haptic ×(Body)Design」をテーマに行いました。
イベントのオーガナイザーである南澤孝太氏をホストに、田中由浩氏(名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 准教授)、倉澤奈津子氏(NPO法人Mission ARM Japan / 理事長)、竹腰美夏氏(NPO法人Mission ARM Japan / デザイナー・リサーチャー)を交えて行われたクロストークの模様をお届けします。
義手など身体に装着する装具のデザインにおいて、ボディイメージ(身体のイメージ図)をどのようにデザインすれば利用する人にとってより自然な「納得のいく身体」を設計することができるかなど、興味深い切り口でトークが展開されました。
※ぜひDESIGNER’S FILEの「倉澤奈津子さん/竹腰美夏さん」、「田中由浩先生」の回をご覧の上お読みください。
自分と機械の狭間のグレーゾーンをうまく技術でサポートする必要がある

ー左から竹腰 美夏氏、倉澤 奈津子氏、田中 由浩先生
(南澤)Mission ARM Japanのお二人からはボディイメージの話から身体をハックするという面白いキーワードをいただきました。デジタルファブリケーションを用いて、自分が納得する身体を作るという発想自体が、非常に新しい概念になっていくのかなと感じました。
身体性をアップデートさせるために、ファブリケーションを始めとした技術がどういうふうに貢献できるか。(障害が)先天か後天かでいろいろ状況は違うと思うんですが、欠損した身体に触感とか身体性の考え方を入れていくと、人が持つ身体性というものがどんどん更新されていき、ボディイメージというものが必ずしも生まれてから死ぬまで一緒のものではなくなるかもしれない。
一方、田中先生のお話では、触覚をどのように情報として扱っていくかっていうところを、「わざと感性の共有」という言葉で表現されていました。
ほかの人の感覚を自分自身の体験として取り込むことで、いろんなものを理解できる、共感できるようになるというお話をいただきました。
まずは、みなさんの触感の解釈について改めて意見をいただければと思うんですが。
(田中)倉澤さんのボディイメージに興味があるんですが。今、右腕の感覚はお腹の中あたりにあるんですよね?
(倉澤)はい、そうですね。
(南澤)それが一番整合性が取れるということなんでしょうか。
(倉澤)元あった手の長さのところに手の感覚がある方が多くいらっしゃいますが、違った形に手の存在があるということもあるようです。
(南澤)田中さんから見て、幻肢痛的な部分に関して何かご意見とかはありますか?
(田中)幻肢痛は多分、基本的に定着しちゃっている。自分のイメージが改変できないので、それが取り戻せないんだと思うんですね。だから、そういう意味では、ラバーハンドイリュージョンもそうなんですけど、身体性って実はぼんやりしていると思うんです。常にフィードバックがかかってるような状態というか。幻肢痛はそれがなくなっちゃったので、しんどい状態なんだと思います。
(南澤)竹腰さんからのお話だと義手をつけると、もしかしたら幻肢痛を緩和することができるかもしれないと。あと、田中さんの話と通じるところがあったのは、リハビリで双方向性での新しい触覚を与えることによって、ボディイメージがどんどんと更新されていくというところがあるんですか。
(田中)多分、そういうことなのかなと思っています。特に一緒に研究を行っている国立障害者リハビリテーションセンターの河島さんとは、先ほどのリハビリテーションに関して「感覚代行リハビリテーション」という呼び方をしていて。触覚が別に取り戻されているわけじゃないんですね。
患者さんの神経は生きていて、脳まで行っているんですが、脳の信号処理がうまくいってない。この情報って、こういうものなんだよっていう再認識をさせてあげてキャリブレーションをしている感覚です。
キャリブレーションをしているので、感覚そのものは取り戻っていないんですけども、現存する能力をうまく使って、それをちょっとアシストしてあげることでちゃんと区別ができるようになってくる。人間は賢いので、どんどんうまく使えるようになってくる。
そういう意味では、先ほどの体の使い方が変わっていくという話と多分一緒なのかなと思います。そこら辺の余白をうまくデザインしてあげることがすごく大事で、技術が全部サポートして、全部できるようになるというのは、何か自分じゃなくなっちゃう気がしてしまうと思うんですよね。そこのグレーゾーンをうまく技術でサポートするっていうのが大事だなと思いながらやっています。
(南澤)その辺、竹腰さんはいろいろな義手をデザインされるときに考えてるかと思うんですが。身体性の余白とか、変化していくことを前提にしたデザインは、どういうふうにされているんでしょうか?
(竹腰)実は最初から身体性を変えようとか狙っていたわけじゃないんですけど、倉澤さんや当事者の方と一緒にいることで、自然と知ってしまったというか、作っているうちに分かってきちゃったみたいな感じなんですけど。
余白を残すっていうことでいえば、倉澤さんの肩はこんな感じで形は作れたんですけど、町を歩いているときに、もし道行く人と肩がぶつかったときに、その感覚がなくて、ぶつかったことに気づくことができなくて、謝りそびれるっていうことも起こり得ると思うんですね。田中先生が作ってた装飾義手のように、センサーが義手側にあれば、ぶつかったことが分かって、自発的に「ああ、ごめんなさい」ってコミュニケーションが取れるとか、そういう余白っていうのが自分の身体として大事なんじゃないかと思っています。

竹腰さんが倉澤さんの左肩を3Dスキャンしたデータを反転し、それを元に3Dプリントして作った右肩用の義手。デザイナーと当事者による二人三脚により製作されている
(田中)皮膚振動っていうのを取り上げましたけど、振動はボディイメージと相性が良い。自分の身体認識には、時間的、空間的な情報の一致っていうのが大事なんです。当たった瞬間に情報が返ってくる。だから、時間がちょっと遅れて返ってくると、もう自分じゃなくなっちゃう。なおかつ、人間が感じる振動って、あんまり精度は高くないんですね。振動があるかないかの精度は高いんですが、ここの位置でこう揺れてるとかいうのは割と鈍いほうなんです。そういう意味では、身体性を高めるための情報ツールとして振動は結構使いやすいと思います。
(南澤)倉澤さんから見て、田中さんの研究はどのように感じますか? 例えばMission ARM Japanの周りにいらっしゃる当事者の方にどういうふうにつながっていくと思いますか?
(倉澤)そうですね。街を歩いていてぶつかったりとか、満員電車に乗って義手の部分が人にぶつかってしまうっていう恐怖感みたいなものっていうのは、結構みんな持っているので、満員電車に乗れない、朝の通勤ができないとかっていうことは話として出たりしますね。例えば女性だったら、つり革を持ったら、片方ないので無防備になってしまうので何となく怖いなっていう感覚があったり。
(竹腰)満員電車のときに、人と人の間をすり抜けるときに、倉澤さんは、自然と自分の肩がないほうの肩が視界に入るようにして、体をひねるようにして移動される印象があります。
(南澤)自然に補完している感じでしょうか?
(倉澤)そうですね。人の間を抜けるときは、どうしてもこう、ないほうから行きますね。感覚がないっていうのをやっぱり認識してるのかなと思う。
(田中)そういう意味では、感覚ってすごく、自他境界を決める役割をもっているんですね。
(南澤)そうですね。
(田中)そのための感覚なので。パーソナリティを決めたりするうえで、触覚はポテンシャルがすごい高いような気がします。
(倉澤)そういえば、やっぱり切断してすぐは、人混みに出るのがすごく怖かったですね。境界線がやっぱり分からないので、怖くて怖くてしょうがなかったという記憶があります。
義手による身体拡張により、その義手をまるで自分の身体のように感じることは可能か?
(南澤)自分の手や体が届く範囲がどこまでかというのは、パーソナルスペースを構築する上ですごく大事になる。
実際の体で届く範囲と感覚的に頭の中にある範囲が不一致になると違和感が発生するのかなと思います。
Hapticsの根源的な意は、倉澤さんがおっしゃったように身体と周りとの境界を認識する、つまり自分の身体の範囲はどこまでなのかっていうのを認識する感覚なんです。だからこそ、例えば道具を持って、その先で物をつつくとボディイメージが棒の先まで延長するっていう話になる。
先ほど興味深かったのは、先天的にひじまでしかない方の場合、その方のボディイメージでは腕の先端がひじの先端であるということ。だから、ひじで何かに触れたり、何かを持ったりすることが非常に自然であるということでした。
竹腰さんから見て、その感覚が延長したり、伸び縮みする可能性は、あるんでしょうか?
(竹腰)そうですね。義手を使い慣れて、道具として完璧に扱えるようになれば、その可能性はあると思います。健常者でも、ペンの長さを、感覚的に理解して、紙に書くじゃないですか。そういう感じで、今井さんが付けてる義手も、これくらい体を伸ばせば届くっていうことをどんどん覚えていって、ボディイメージとまではいかないけど、何か一体化に近い状態にはなるのかもしれないですね。ただ、普段義手を使わないで生活をしている方だと感覚が延長していったり、伸び縮みする可能性というのは低くなると思います。
(田中)義手の実験をやってると、最初にあった手の感覚がだんだん伸びてきたという人がいます。感覚はなかったのに、触って、情報が返って来てというのを繰り返すと、「ああ、ここが、自分の境界なんだ」という認識が高まっていきます。
ただし技術的によく分かっていない部分が結構多くて。
先ほど竹腰さんがおっしゃられたように、義手だって外すこともあるし、ずっと付けてるわけじゃないですよね。外すと、自分の身体は劇的に変わってしまうわけで。それが情動や心身にどう影響するかというのは、しっかり考えていかないと、逆に負担になってしまう可能性も考えられます。
(南澤)確かにそうですね。最初に腕を失ったときの変化に近いものが、日々生じてしまう可能性ということですよね。
(田中)そうそう。
(南澤)だから、単に腕を伸ばそうとするならば、触覚を使うと非常に有効なはず。でも確かに、外すって行為が必ず入るっていうのは、盲点でした。
(南澤)倉澤さん、肩の義手も外すと、感覚がやっぱり変わるんですか?
(倉澤)例えば、腕時計を忘れたとか。外に出るときに必要な物を、「あっ、今日してない」っていうような感覚に近いんですね。最初は人にどう見られるかっていうのをやっぱり気にしてたとは思うんですけれども。今はもう、それが自分なんだっていう認識なのかなと。
(南澤)眼鏡をかけてるのを忘れて、眼鏡を探しちゃうようなもんですよね。
(倉澤)そうですね。
(田中)眼鏡を外すと急に世界が変わって、眼鏡をかければ、急に眼鏡の世界に戻れるわけですよね。人間って、結構柔軟な側面もあるんだなぁと思います。ただ、どういうところが危なくて、こういうところは結構うまく人間はやってくれるという線引がわかれば、より当事者にとって扱いやすく納得がいく義手をつくることなどにつながるんじゃないかと思っています。
当事者とデザイナーの協業により、身体の納得感をデザインする
(南澤)身体の納得感に関して腑に落ちる瞬間っていうのは、どういう風に感じるんでしょう?
(竹腰)多分、今もベストではないと思うんですよ。だから、あえて満足という言葉は使わなかったんですけど。納得を得るときに、デジタルファブリケーションとかは役立つと思っているんです。いわゆるオーダーメイドで「こういう義手を作ってください」って頼んで自分の見えないところで作ってもらうだけでは、「何でこうなったんだろう?」や「こういうところが納得いかない」といった要望を反映させることができません。でも、一緒に作っていくっていうことで自分も試行錯誤して「これがいいんだ」「こうしたくなってきた」とか、そういう過程に参加するから、納得する身体になるんじゃないかなと思ってて。Fabしたものが、納得する身体になって、眼鏡が身体の一部になるみたいな感じになっていったらすごいなと思っています。
(南澤)そうですね。触覚の納得感、多分ありますよね。
(田中)あると思います。
(南澤)これからは自分の感覚や身体の納得感をデザインすることが、たぶんできるようになってくるんでしょうね。
(田中)そうですね。そういう意味では、竹腰さんが言ったプロトタイピングをFabするってすごい重要。
(南澤)身体の話だから、やっぱり自分でつくってみないと分からないですね。
(田中)そうですね。
(南澤)それに、プロセスの中で、自分もそこをアディショナルな身体に対してマッチングしてくるし、インピーダンスマッチング(着けているのか着けていないのかがわからないくらい自分の身体に馴染んだ状態)が取れてくるし。そのプロセスを経ていくごとに、お互い寄っていって、最終的にはアップデートする。
(田中)まだ触覚の分野っていうのは実験的な領域で、方程式が見つかってない領域ですね。だから、実験を重ねて、それぞれのケースというのを作っていって共通項や異なる項目を見ていくと、きっと体系的なマップが出来上がっていくんだと思います。きっとそれは多様性があるんだけど、「これをやりたかったら、こういうルートだよね」とか、何かそういうマップづくりみたいな。
そしてそこにちゃんと関係性を作っていくことが、ものすごくデザインには重要なんじゃないかなと思いますね。
質疑応答
(南澤)そうですね。ありがとうございました。フロアのほうから質問をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
(お客さんA)2つほどあるんですけど。まず、すごい楽しかったです。ボディイメージと身体性という言葉が度々、両者のスライドの中に出てきて、多分その定義が何かふわっとしてるなというところが引っ掛かっているんで。まず、その身体性とは何か、ボディイメージとは何かっていうのをそれぞれ定義してほしいなというのが1つと。2つ目の質問は、バーチャルリアリティ、最近はやってると思うんですけど。田中さんのスライドで初めに言われた「自己言及性」と「双方向性」が、バーチャルリアリティはまだ両方ないんじゃないかなあと思っていて、バーチャルリアリティを使って幻肢痛を解決しようとか、ボディイメージを変えようみたいなアプローチがたくさんされているんですけど、今のバーチャルリアリティだとその2つを満たしてないから、何か下手にやっちゃうと悪化するんじゃないかという懸念もあって、そこに対するコメントをもらえればなと。
(田中)まず、身体性とボディイメージの定義は、すいません、私もはっきりできません。ボディイメージは、多分自分の頭の中で思ってる自分の体のイメージ図だと思いますね。自分の手が5本あってとか。子供とかでいうと面白いですよね。ちっちゃい子だと、「ほら、指の数を数えてみて。5本あるよ」って言って。「あっ、本当だ!」と言うんですよね。そういう「自分の体、こうなってる」っていう図式のことだと、私は認識しています。で、身体性っていうのは、何でしょうね? 定義は多分、ちょっと人によって多分違うのかなと思うんですけど。私は、その触覚が自分の体を通じて得る感覚? 運動も込みの。だから、そこを身体性と私は呼んでいます。だから、南澤先生の研究室の名前「身体性メディア」っていうのはまさしくそうだなって。「感覚の中で身体性メディア、どれに該当しますか」っていうと、「それは触覚ですね」って。そういう意味で私は身体性って使っています。
先ほどのバーチャルリアリティの話は、まさしく私はそうだと思っていて。自分の手でないし、自分の皮膚特性でもないし。硬い皮膚、柔らかい皮膚もあるので、うまくそれを入れてあげたりとか。あとは、双方向性ですよね。リハビリの方ではちょっとずつ今は出始めています。ロボットを使って、自分の手が動こうとするとロボット側が動いて、それで感覚のフィードバックも返ってきてっていうのが、ちょっとずつ入ってきています。まさしく、多分その2つを入れてあげると、すごくリッチになるし。逆に入れないっていうことが、ある種の違うボディイメージで身体認識をつくっちゃうっていうことにも繋がってしまうかもしれないと思ったんです。
(南澤)竹腰さんはいかがでしょうか。
(竹腰)これも、もしかしたら違うのかもしれないんですけど。ボディイメージは、まさに体のイメージ図です。で、身体性については、身体の能力といいましょうか、手であったら「わざ」、わざの習得。多分触覚と経験値、経験則みたいなのが関係していると思うんですけど、それに基づいた体の能力というように定義しています。
(南澤)多分ボディイメージに関しては、基本的には脳内認知の話で。頭の中で自分の身体というものを、どういう形であって、今、どういうポジションにあって、それがどういうアビリティを持っているかっていうものを脳内で実際に持っている。ある種シミュレータのような働きをもっているのだと思います。身体性に関しては、どちらかというと、やっぱり外界との関係性みたいなものですね。運動とか、「わざ」とかいう言葉が出てきましたけど。実際、それが外界とか、あるいは他者に対してどういう機能性を持ってどのような影響を与えるかっていうところと、外界からどういう影響を受けるかっていう、多分そのループっていうものが、身体を通じて回っていく。もともとギブソンっていう方が1960年代ぐらいに言ったHapticsの語源は「身体と通じた外界の認識がHapticsだよ」と言ってたらしいです。そう考えると身体性っていう言葉に近いものなのかなという気がします。身体性は多分、分野によってかなり実は違う定義で言ってるところはあるんですけど、割とそういう感じの認識かと思っています。
ほかにご質問はありますでしょうか。
(お客さんB)すごい興味深いお話をありがとうございました。今、もともとあるものであったりとか、使いやすいものみたいな話が中心だったと思うんですけど。体に対して、ほかの器官を増やしていった場合の身体性の変化みたいな話にすごい興味がありまして。実際に脳波で動く猫耳とか尻尾を作ってきた経緯があるんですけれど。そのときに、脳波で動く尻尾というのを1回作ってデモしたときに、1日デモしたあとに外すと、尻尾があった自分の感覚っていうのがすごい残るっていうことを感じたことがありました。何かそういう、本来あるはずがない器官を人間が手に入れていくような可能性っていうのは、あるのかなというのをちょっと田中先生にお伺いしたいと思います。
(田中)あると思います。人馬一体とか、車もある種、乗ったときに感覚が外まで広がるっていうことがあると思います。なので、触覚を使うとすごく楽しい世界が待ってるんじゃないかなと。いろんなことができるようになるんじゃないかなというふうに思っています。
(南澤)ちょっと、竹腰さんのお話の中でご紹介いただいたので。僕らが最近やってる、まさにその体を増やしてみるっていう研究をご紹介しようと思います。「MetaLimbs」といって、3本目と4本目の腕をつくろうという話なんですけど。3本目と4本目の腕を体につけていて、それを足で動かすんです。
(南澤)僕はちっちゃいときに入院してたことがあったんですが、足でそのまま物をつかんで、手に受け渡して拾うみたいなことをよくしてたんですけど。そうすると、足もだんだん手っぽくなってくる。今、これでやったことは、3本目と4本目と、腕をロボットでつくって、足をグッパーすると、腕もグッパーする。足を動かすと、手も動く。そのロボットハンドで物をつかむと足にちゃんともってる触感が返ってくるようにすると、足を動かしてるんじゃなくて、そこにあるロボット、第3の手を動かそうとしたときに、無意識的に足を動かそうとするようになってくるんです。今、身体拡張っていう文脈だと非常に、Mission ARM Japanさんがやられている話とか、田中さんがやられてるような話っていうのが、自分の本来持っているボディイメージを外側に展開させたときにどうなるかっていう話とつながっていて、そのときにもやっぱり、自分のボディイメージの拡張っていうときに、その触覚の双方向性っていうのが非常に利いて、それがないとやっぱり駄目なんです。ないと、あくまでも道具の域を超えないんです。双方向性があることで、そこにインタラクションが生じた瞬間に、身体として接続し始める。慣れてくると、だんだんだんだんそれが身体の一部として感じられるようになる。これはすぐに外すんですよ。しばらくやったら外すんですけど。でも、何かそれが記憶として残っていて、また付けると、そのアップデートされた身体ボディイメージにまた戻れるみたいっていうことが、何となく僕らも最近分かり始めています。
田中先生、倉澤さん、竹腰さん、本日はどうもありがとうございました。
ゲスト

倉澤奈津子(NPO法人Mission ARM Japan / 理事長)
6年前に骨肉腫で右腕を肩から切断。以来、左手生活の甲斐あってかクリエイティビティが爆発。がん患者で作った「患者会上肢の会」を2014年にNPO法人Mission ARM Japanとして設立。コミュニティ活動を軸に、自らの欲しい肩をつくるために「肩パッドプロジェクト」をプロデュースする。

竹腰美夏(NPO法人Mission ARM Japan / デザイナー・リサーチャー)
1992年 北海道札幌市生まれ。2014-15年FabCafeのFabスタッフを経て、2016年よりMission ARM Japanにて義手や装具のデザイン開発に従事。2017年HAPTIC DESIGN AWARD入選。Fabと人間の創造性・身体性の拡張に関心を持ち研究する傍ら、デジタル技術を用いた表現やデザイン活動も積極的に行う。首都大学東京大学院博士前期課程在籍。慶應義塾大学SFC研究所 所員。
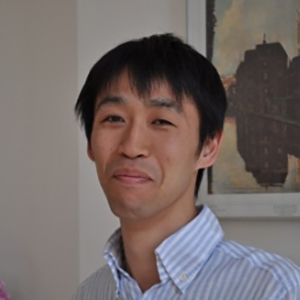
田中由浩(名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 准教授)
2001年東北大学工学部3年次に大学院に飛び入学、
ホスト

南澤孝太(みなみざわ・こうた)
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD) 准教授。2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻博士課程修了、博士(情報理工学)。 触覚を活用し身体的経験を伝える触覚メディア・身体性メディアの研究を行い、SIGGRAPH Emerging Technologiesなどにおける研究発表、テクタイルの活動を通じた触覚技術の普及展開、産学連携による身体性メディアの社会実装を推進。 日本バーチャルリアリティ学会理事、超人スポーツ協会理事/事務局長、JST ACCELプログラムマネージャー補佐を兼務。
TEXT BY KAZUYA YANAGIHARA