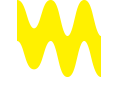2017.03.30
筧 康明(慶應義塾大学環境情報学部准教授) 世界とのインタラクションをデザインする
〜“実世界をスイッチする感覚”は、いかにしてつくられたか〜

筧 康明(かけひ・やすあき)
1979年、京都府生まれ。2002年東京大学工学部電子情報工学科卒業。2007年、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。2008年から慶應義塾大学環境情報学部専任講師を経て、現在准教授。 2010年にインタラクティブアート制作を手がける、株式会社プラプラックスの取締役に就任。2015年Massachusetts Institute of Technology(以下MIT)訪問准教授。
主に、Computer Human Interaction、メディアアート、Augmented Reality(拡張現実感)技術などの分野で研究・制作に取り組む。これまでにSIGGRAPHやArs Electronica Festivalなど国内外の学会、コンペティションで研究・作品を発表し、受賞も多数。
学生のころよりメディアアーティストとして活動し、現在のようなプロジェクションマッピングの誕生を予知していた筧 康明さん。モノの素材特性とデジタルテクノロジーを掛け合わせたインタラクティブメディアの開発を行う研究者でありながら、現在もメディアアーティストとして、さまざまなインタラクティブアートを手がけている。
「研究者なのか、メディアアーティストなのか、コンセプターなのか……。むしろ何者にもならない方法を探している」と筧さん自身が語る通り、端から見ると幅広すぎる活動も、「僕としては同じ“インタラクション”」とシームレスにやってのける。言わば“越境の研究者”とも言うべき彼の活動に迫ります。
ご自身の研究分野におけるHAPTICS(触覚学)と、
その位置づけについて教えてください。

父が京都で染め物など伝統工芸の仕事をしていたこともあり、80〜90年代のデジタルブームにまったく乗らず、古い物を大切にする家庭だったんです。当然家にはコンピュータもなく、ファミコンも買ってもらえなかった。だから当時ファミコンに夢中だった友だちの気を引くため、小学校にあった「昔の遊び倶楽部」というのに入って、昔の遊びを今風につくり変えるってことをしていました。そのあたりに、昔の遊びが持つフィジカルなものづくりと、ファミコンのような画面の中の世界に対して、どうやって実世界の人たちの興味を引くか、と考えることの原体験があったんでしょうね。
大学に入ってからもコンピュータと深い接点を持つことなく、20歳くらいまで触ったことがなかったんですが、90年代後半、世の中にインターネットやIT革命という流れが出てきて、ドラスティックにものづくりの流れが変わっていく風を感じたんです。ちょうどそのころ八谷和彦(はちや・かずひこ)さんや岩井俊雄(いわい・としお)さんといったメディアアーティストの方々のお話を聞く機会があったんですが、彼らの作品にはこれまで苦手意識のあったコンピュータのイメージを覆す、あたたかさや身体性があった。その影響もあり、いざコンピュータに触れてみると、コンピュータが持つ即時性や、改変可能でその場ですぐ体験を共有できる感覚に、すっかり魅了されてしまったんです。
研究室に入ってからは、コンピュータとフィジカルな表現やモノづくりの境界にいたくて、VR(バーチャルリアリティ)の研究をはじめました。ちょうど4年生になったころ、2000年くらいからはメディアアートという言葉も知らず、今でいうプロジェクション・マッピングのような視覚装置をつくったり、街中に投影したりして人の行動を起こす研究をしていたんですが、近森 基(ちかもり・もとし)や久納鏡子(くの・きょうこ)と出会い、メディアアートを手がける「plaplax」というチームをつくることになりました。そこから、体験型の作品をつくることを始めたんです。
そもそもプロジェクションの作品でも「実世界に別の見方を与える」ような体験を目的としてたので、だんだんと(投影される側の)マテリアルに興味がわいてきて、その後は、どうやって素材の特性を引き出していくかにシフトしていきました。そう考えると自分はずっと、“実世界で、感覚をスイッチするためのテクノロジー”を研究対象としているんです。HAPTICSのデザインをするというときにも、触覚デバイスをあらゆるプロダクトやシーンに持ち込めばいいとは思っていなくて。HAPTICSを新しい発見を促す装置と捉えて、そこを経由すればあらゆるもののつくられ方が変わっていく、そのことに興味があります。
触覚においては、現在どのような研究を行っているのですか?
いまだに自分が研究者なのか、メディアアーティストなのか、コンセプターなのか……。むしろ何のラベルも貼られず、何者にもならない方法を探している感じなので、研究者的答えができるかわかりませんが(笑)、一方では研究者としてプリミティブ(根本的)な研究活動をし、もう一方ではメディアアーティストとして、作品を通じて、人と人をつなぎ価値を見出していく活動をしています。
HAPTICSの関連で言うと2007年から慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の仲谷正史(なかたに・まさし)君や南澤孝太(みなみざわ・こうた)君らと「TECHTILE」の活動を始めたんですが、2010年あたりから山口情報芸術センター(YCAM)とコラボレーションすることになりました。ちょうどその頃、YCAMではダンサーの安藤洋子さんらが「Reactor for Awareness in Motion(以下RAM)」というプロジェクトを展開されていました。これは、トップダンサーの踊りの身体感覚を、一般の方にも育むためにVRなどのデジタルテクノロジーを利用するというもので、僕も途中からダンサーと環境とのインタラクション部分のディレクションと研究開発を主に担当することになりました。
ダンスは何かを避けるときなど必然性のある動きが圧倒的に美しい。トップダンサーは無意識にそうできてしまうんですが、それを一般の方にも体験してもらうために、映像でキューブを出してそれを避けながら踊ってもらうとか、自分の体とほかの人の身体がくっついたようなイメージを投影するとか。次にどういう動きが必要といった振り付けがわからなくても、自然に身体が動いていくようにデジタルテクノロジーを使ってみよう、という実験でした。
最終的にはRAMの最終公演の技術担当として舞台も一緒につくることになったんですが、これは今流行りの“ダンサー × プロジェクション”のように、ダンサーを引き立たせる装飾としてのVRではなく、ここでのテクノロジーの役割は、あくまでダンスのメソッドの共有と身体性の拡張。なので、テクノロジーを通じて身体の動きと感覚が育まれると、最後の舞台ではテクノロジーを用いずとも、生身の人間が踊ることが一番美しい、という見せ方ができた。このように新しい身体感覚や表現、関係性をつくっていくための触媒として、テクノロジーの使い方を追求しています。
またこのプロジェクトは、個人的に行っている障害者の方とのリハビリテーションの新しいプラットフォームづくりにも通じています。この活動では、多くの人に見てもらう作品や研究とは対象的に、ひとりの人間に対しデジタルテクノロジーがどう貢献できるのか、という思いで始めました。
たとえば毎日の手の動きを加速度センサーで記録するリハビリカレンダーだったり、肘の動きをサポートすると同時にコンピュータで記録してリハビリを楽しく補助する肘当て。これまで自分がやってきたことを、フルコースではなく“まかない飯”のように即興で出して、本人のアイデアも聞きつつ、完全にその人のためだけのデバイスをつくっています。これがRAMの活動と通ずるのは触覚デバイスと身体の関係性。つまり“身体をサポート”するのではなく、“身体をデザイン”している、という部分なんです。実際、被験者のリハビリへのモチベーションもすごく高いんですよ。なにせ本人が自分の身体の一部をデザインしてますから。
ご自身の研究とHAPTICSがもたらす
未来の社会、産業、生活の可能性とは?

現在の研究は、学部生のころから興味のあった材料工学がメインです。素材と触感は通常セットになっているものですが、そこを切り離すことができたらおもしろいと思っています。たとえば“柔らかい鉄”や“あたたかい氷”とか。ここ数年でようやく、情報工学と材料科学が密に繋がってきていて、物質の特性のコントロールが可能になってきています。
僕らもある種デザイナー的視点から、硬さ・柔らかさやカタチ、テクスチャーが動的に変わるマテリアルをつくる研究を進めていて、それによってどんなフィジカルインタラクションが可能かを追求しています。実はそれって、触覚や感覚をつくることそのものであり、“モノの存在”はもちろん、ひいては生活そのものを劇的に変えることができるのではないかと思っています。
いわゆるプロジェクションマッピングやARは、すでに当たり前のテクノロジーになって、作品をつくる際にも使いたいときには使える状況になっているので、いったん今は研究に振り切って、マテリアル(材料科学)に踏み込んでみようと思ったんです。最近では、伝統産業の方と一緒にプロジェクトを始めたりしていて。なんだかんだ子どものころの原体験であるモノに戻ってきた感じはあるかもしれません。
研究内容を社会実装していくうえでのデザインについて、
どう捉えていますか?

2015年にはMITメディアラボで研究をしていたのですが、近年盛んに研究が行われているスペキュラティブデザインやヴィジョンドリブンリサーチなど、「未来やヴィジョンを見通しながら問題提起や新たな提案をしていくか」という考え方には、MITのなかでもいろんな軸(考え方)が混在していました。たとえば、SF映画のように具体的なフィクションをつくることで、実際の未来がカタチづくられるという考え方。また一方では、現在に作用するものをつくらなければ意味がない、とする考え方。ここでのディスカッションを、日本に戻ってからも意識して活動しています。
特にこれからの日本では、ラボでの活動をビジネス含め、社会や生活の中で実際に作用させていくかが重要だと思います。ときには“まかない飯”のように、ときには”フルコース”のように。たとえば真鍋(大度)さん率いるRhizomatiksのように、クライアントワークなど制約がある中でも、自身の作家性やR&D(研究開発)を盛り込んで、ものづくりをしていく必要があるのではないでしょうか。僕自身も論文やワークショップ、展示などを個別に考えるわけではなく、作品や展示のフィードバックを取り込んだ研究内容が社会に影響を及ぼすような、いわばアウトリーチの展開を意識して活動しています。
もっとも素敵なHAPTICSだと思う、
世の中のモノゴト(事例)とは?
僕は身体が硬いわりにストレッチが好きで、気持ちを切り替えたいときや何かを考えたいときに、よくストレッチをします。ストレッチをすると、身体の状態がどんどん変化して、最終的にはピタッと身体が床につくようになります。そのとき、環境と身体の関係性が融けて変化していくように感じるんですよ。それって、HAPTIC的だなと思って。自分の血液を感じることができる、あの感覚が好きなんですね。

TEXT BY WATARU SATO
EDITED BY MASARU YOKOTA(Camp)
PHOTOGRAPH BY HAJIME KATO