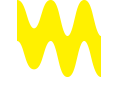2017.11.04
触覚と社会はどう結びつくのか?
Haptic ×(Social)Designの実践手法を語る(中編)
〜ゲスト:渡邊 淳司、太刀川 英輔/ホスト:南澤 孝太〜
“わざ”にフォーカスし、Haptic(触覚)の研究やデザインに携わる方々をゲストに開催するシリーズイベント「Haptic Design Meetup」。2017/11/4に実施したVol.5は「Haptic ×(Social)Design」をテーマに行いました。
イベントのオーガナイザーである南澤孝太氏をホストに、渡邊 淳司先生(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)、太刀川 英輔さん(NOSIGNER)を交えて行われたクロストークの模様をお届けします。
※肩書は2017年11月4日登壇当時のものです。

ー左から南澤 孝太氏、太刀川 英輔氏、渡邊 淳司氏
人はそれぞれに違う触感を感じているのか?
(太刀川)触覚って、僕の感覚では、そういう質感のいいもののように、少なくとも擬態することができるじゃないですか。それがどんなに新しいものであったとしても、そこに革を巻くだけで、何かクラフト感のあるものっぽく見えることがある。これは結構重要なことだと思っていて。というのは、さっきも言ったとおり、デザインで伝えられる情報っていうのは少ないんだけれども、あるタイミングでフィットさえすれば、それがスムーズに流れた暁には、ものすごく意味を持っていくというタイプのコミュニケーションだとすると、伝えたい新しい部分のほかに、今までどおりですよっていうコミュニケーションが要される部分ってすごくあるんです。
逆に言うと、今までのものから、全部が全部を変えるんじゃなくて、一部今までの文脈を引き継いでるという姿勢を見せることによって、安心して使ってもらえるようになることがよくあるんですよね。
(南澤)フィットするというか手触り感がある感じにすることによって。
(渡邊)体で触れたときに、そのもの自体が溶け込んでくるんでしょうね。
(太刀川)それもあるし、ほかのもので経験してるからですかね。
(南澤)違和感を感じないで済むんだと思う。
(太刀川)何か高級なパッケージっていったら、ザラザラしたところに、何かピカッとした箔が押してあるって、僕らは知ってるんですよ。それをハックすると、高級じゃないもので、ものすごく高級なペットボトルができる可能性もあるわけです。表面にそういう質感を与えることによって、ただの水なんだけど、その表面が擬態されることによって、ウィスキーのように高級なただの水ってことがあり得るんですよね。そうすると、ウィスキーの値段で水が売られることができる瞬間が出てくるんですよ。
(渡邊)お茶のパッケージも結構いろいろありますよね。
(太刀川)竹型のデザインとかもありますよね。
(渡邊)竹の形で、持ったときにちょっと重い。すごくフィットするし、あと外に巻いてあるプラスチックのところに質感をつけていて、持ったときにぬくもりがある感じになっていたり。
触れなくとも感じる
Haptic Designは存在するか
(太刀川)これ、僕がデザインした日本酒なんですけど、どう見てもシャンパンに見えませんか?原寸のレモンをむいたその形のまんま、ペタッと貼ってあるんです。これ、スパークリング日本酒なんです。

ミカド レモン。レモンの皮の色味だけでなく、質感までもが再現されている
これは2つの擬態をしていて、マーケットが日本酒ではないっていう擬態をしてるわけですよ。今までのスパークリングワインの代わりに飲んでねっていうことを、そのボトルやタイポグラフィーの質感を通してやってるし、明らかにオーガニックのレモンの話ですっていうことは、これを見りゃ分かるっていうことをやっていて。だから、これは擬態なんですよ、これはレモンの皮そのものじゃないんだけど、でも、そういうふうに触感がないところに触感を与えていくことによって、それそのものとして伝わるコミュニケーションが、そのレモンを一番伝えたいからレモンそのものの触感をしていたら、伝わるに決まってるということなんで。
(南澤)僕らはそのボトルに触れてないんだけれども、明らかにレモンの質感を想起できるわけじゃないですか。さっきの空間の話もそうなんですけど、実際に触れてないんだけれども、その触れ感というか手触り感がものすごく感じられることが何かコミュニケーションにデザインとして意味を持ち始めている。その触れない触覚っていうキーワード、ちょうど前回のこのMeetupでも出てきたキーワードなんですけど、人と人が会ったときに何かその間でぞくっとくるっていうのも含めて、あえて触覚を導入するんだけれども、別に触れてるわけではないんだけど、確かに伝わるって、このプロセスって一体何が起こってると思いますか?
(太刀川)多分僕らの触覚的・物性的記憶の話にさっきのところで結び付いてくるんですよ。僕ら生きてきた中で、もう数えきれないほどのテクスチャーを触ってるわけです。1日100個は最低でも触ってるんだとすると、それ1年間に3~4万個は触ってる計算になりますよね。そのテクスチャーを触っていけば触っていくほど、脳にはそういう状態のテクスチャーとこの記憶っていうのがいっぱい蓄積されていて、だから、革に詳しい人だと、高級感のある革と安っぽい革、物性としては何も変わらない2つの間の違いをちゃんと把握することができるようになったりするんです。なぜかそこから、「あっ、これは丁寧に作られている」とか、「これは雑に作られている」とか、同じ素材のように見えるし、ものの特性上はほぼ同じところに属するものであったとしても、なぜかそこに掛けられた人の手が全然違うこともなぜか分かっちゃうんですよね。多分そのテクスチャーが出来上がっていく文脈と、触ったテクスチャーがつながっているから。
(渡邊)これ、例えばビジュアルをデザインするときのプロセスと、触れて感じるものをデザインするときのプロセスって、やっぱり違ったりするんですかね?ワークショップを触覚でやったりすると、「ほら、これだよ、これ」って言っても絶対伝わんないんですよ。そうだけど「はい、これ。どうぞ触って」っていう、そこのやりとりがすごい必要な感覚がしていて。それは、さっきの個人差があるし、それは同じ触り心地も違う言葉で言ったりするので、みんなで合意形成をする過程がすごいある気がしたんです、触覚について考えなきゃいけないってなった途端に。
ちょっとビジュアルデザインは全然分かんないんですけども。どっちかっていうと、触覚はまだ、そのまま伝えることもできないし、その中でわれわれはどういうふうに解を見い出すかっていうことをすごい考えさせられたんですよ、ワークショップをやるたびに。何かこう同じのを触って、「はい、これどこ?」とかやって、「どんな感じ?」っていうと、みんな違うこと言って。「赤は赤じゃん」っていうような人とか、もちろん差はありますけれども、そこの何かゆがみ、揺れというか、そういうものがすごいありましたね。
(太刀川) 基本的には、デザインをするときには、ビジュアルと触覚はセットなんですよ。だから、同時にしか考えないんですね。僕はデザインを使ってUXを設計する立場としては、その2つは絶対につながっちゃうんですよ。テクスチャーだけが浮き彫りになることはないんですよね。テクスチャーだけがないし、ビジュアルだけが浮き彫りになることはなくて、デザインはかっこいいはずなんだけど、間違った紙に印刷したことによって、かっこ悪くなっちゃうことっていうのは、よくあるんですよ。
(南澤)この絵を見てる、ここにいる60人以上ぐらいの人たちが何を受け取ってるかっていったときに、実は差があるのか、やっぱりでも同じものを受け取ってるのか。多分太刀川さんの立場からだと基本的には同じものを受け取る、伝えているっていうような立ち位置になるのかなっていう気もしてるんですね。
(太刀川)そうですね。僕は割と共感覚として、そういう物性に対する理解をみんなもう生まれながらに生きている間に持っているっていう前提があるから、だから、こういう質感を再現したら高級感につながるとか、こういう質感を使うことによって未来感につながるとか、そういう出したい感覚とこのテクスチャーははまっているかっていうのは、もう、当然素材についてよく知らないと、そこをハックはしにいけないけど、でも、みんなの中に何でかそう思うっていう言語はもうできてるんで、それは暗黙知的な言語だけど。
(南澤)多分、建築的な考え方があるんですね。その中に多人数が同時にたくさん存在してるってことを大前提にした上で、そういう人たちに何を空間によって伝えるのかっていうところだと思うんですよ。多分淳司さんのお立場から見ると……。
(渡邊)逆に受ける側から考えると、それはそうかもしれないけど、僕は違うと思うんですよね。
(南澤)そういうことですよね。
素材の触覚に対して感じる思いは
万人にとって共通なのか?
(渡邊)触覚そのものの話ではないですけれども、2017年1月に『ウェルビーイングの設計論』という本の監訳をやらせてもらいました。ここで触覚から一瞬だけ離れますね。
この本は、テクノロジーは本当に人を幸せにするのかということがテーマなんですが、そういうことを考えて、先行研究とかをいろいろ調べるわけです。ポジティブ心理学という分野がありますとか。分類することも考えましたが、すごい難しいと。なぜか? 僕が何となく感じてることを3つ挙げます。「ウェルビーイングは人によって異なる」、「ウェルビーイングは与えられるものではなく、自分で気がつくもの」、「ウェルビーイングを実現することがゴールではない」です。この1つ目「ウェルビーイングは人によって異なる」は当たり前のことです。例えば海外の人はやっぱり違うし、日本的なものと西洋的なものも違うんでしょう。ウェルビーイングの話をしていると「それはそうかもしれないんだけど、俺らのこと何も分かってないよ」って言われることもあります。このことは触覚にもいえるんじゃないかなと思うんです。
(太刀川)その話でいくと、ちょっと僕の説明が乱暴だったところなんですけど。必ずそういう共感覚が生まれる保証はないですね。例えば、同じ革を触って、この革が好きな人と嫌いな人がいるんですよ。そういう意味において、そこで得られる、素材から得られる感覚っていうのは、その人の個人的な記憶と結びついてるから、これは駄目なんですよね。
ただ、それが革だということは、全員に伝わるんですよ。これは結構重要なところで。要するに、どういう物性、どういう組成のものであるかっていうことを設計するっていうのは、そういうことなんですよね。革という素材が想起しやすい記憶とか、アルミという素材が、ステンレスという素材が、真ちゅうという素材が想起しやすい記憶っていうのは、これはまた全然違うんですよね。例えば真ちゅうのほうはアンティークな感じがするから、何かちょっとおしゃれアンティークっぽいカフェに行くと、真ちゅうのものが結構あるみたいなことがあったりするんですよね。
あとは、ものが出来上がっていくそのものの加工のプロセスの進化によって新しいテクスチャーはずっと出続けてきてるわけじゃないですか。要するにホログラムとかなかったし、今度有機ELみたいなのが当たり前になってくると、ブラウン管を「古くねえ?」っていうふうに思う時代が来るとは思わなかったんですが、もう画面を見ただけで「古くねえ?」って思うわけです。それは、ザラザラ感によってなんですけど。だから、何かその物性の裏で働いてるものを読み取る力として、人間が動物として生きていかなきゃいけないから、そういう危険なものから逃れるとか、より自分にとって良さそうなもの選ぶとか、そういうことのために触覚が発達したので。
(渡邊)そうですね。多分、レイヤーがあって、そのもの自体だったりとか、それが何であるかみたいなレイヤーに対して、触覚ってそこから人の記憶を呼び起こすとか、その身体、直接的に感情だったり何なりに働きかける要素があると。まさにエンジニアリングとして、デザインとしてちゃんと伝える部分と、それに対して個人化の部分の両方を考えていく必要があるだと思います。同じものを見たら、やっぱり高級っぽいのが高級っぽいと感じてると思います。ただ、その背後にあるその人の記憶とか思いみたいなものをどう拾い上げられるのかみたいなところまでやっていく必要があると思っています。
後編に続きます。

渡邊淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 感覚表現研究グループ 主任研究員)
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 主任研究員(特別研究員)/東京工業大学工学院特任准教授兼任。博士(情報理工学)。人間の触覚の知覚メカニズム、感覚を表現する言葉の研究を行う。人間の知覚特性を利用したインタフェース技術を開発、展示公開するなかで、人間の感覚と環境との関係性を理論と応用の両面から研究している。近年は、学会活動だけでなく、出版活動や、科学館や芸術祭において数多くの展示を行う。主著に『情報を生み出す触覚の知性』(毎日出版文化賞(自然科学部門)受賞)がある。

太刀川英輔(NOSIGNER代表 / 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特別招聘准教授)
ソーシャルデザインイノベーションを目指し、総合的なデザイン戦略を手がける。建築・グラフィック・プロダクト等への見識を活かした手法は世界的に評価されており、国内外の主要なデザイン賞にて50以上の受賞を誇る。東日本大震災の40時間後に、災害時に役立つデザインを共有するWIKI『OLIVE』を立ち上げ、災害時のオープンデザインを世界に広めた。その活動が後に東京都が780万部以上を発行した『東京防災』のアートディレクションへ発展する(電通と協働)。
ホスト

南澤孝太(みなみざわ・こうた)
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD) 准教授。2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻博士課程修了、博士(情報理工学)。 触覚を活用し身体的経験を伝える触覚メディア・身体性メディアの研究を行い、SIGGRAPH Emerging Technologiesなどにおける研究発表、テクタイルの活動を通じた触覚技術の普及展開、産学連携による身体性メディアの社会実装を推進。 日本バーチャルリアリティ学会理事、超人スポーツ協会理事/事務局長、JST ACCELプログラムマネージャー補佐を兼務。
※肩書は登壇当時のものです。
TEXT BY KAZUYA YANAGIHARA